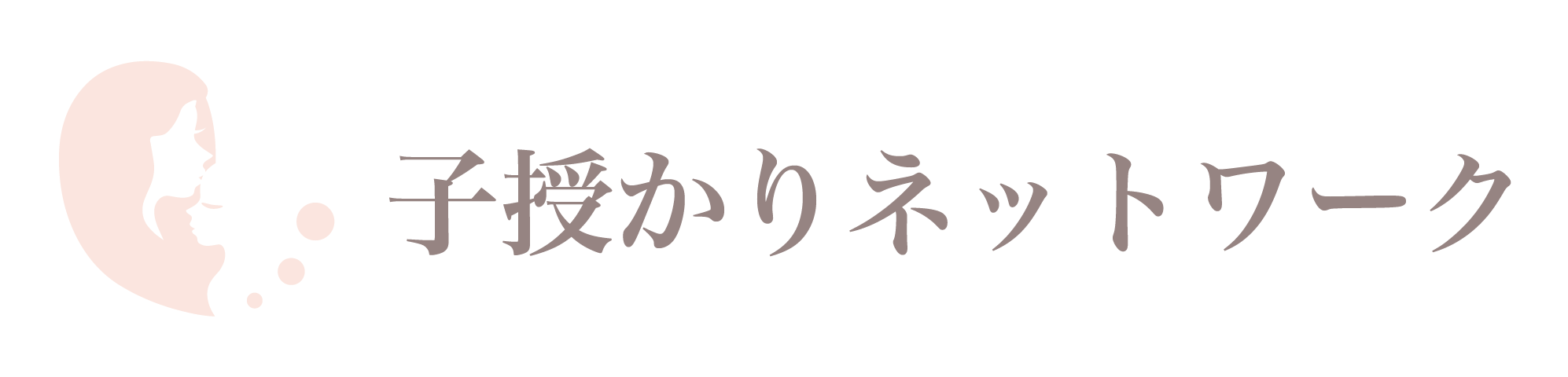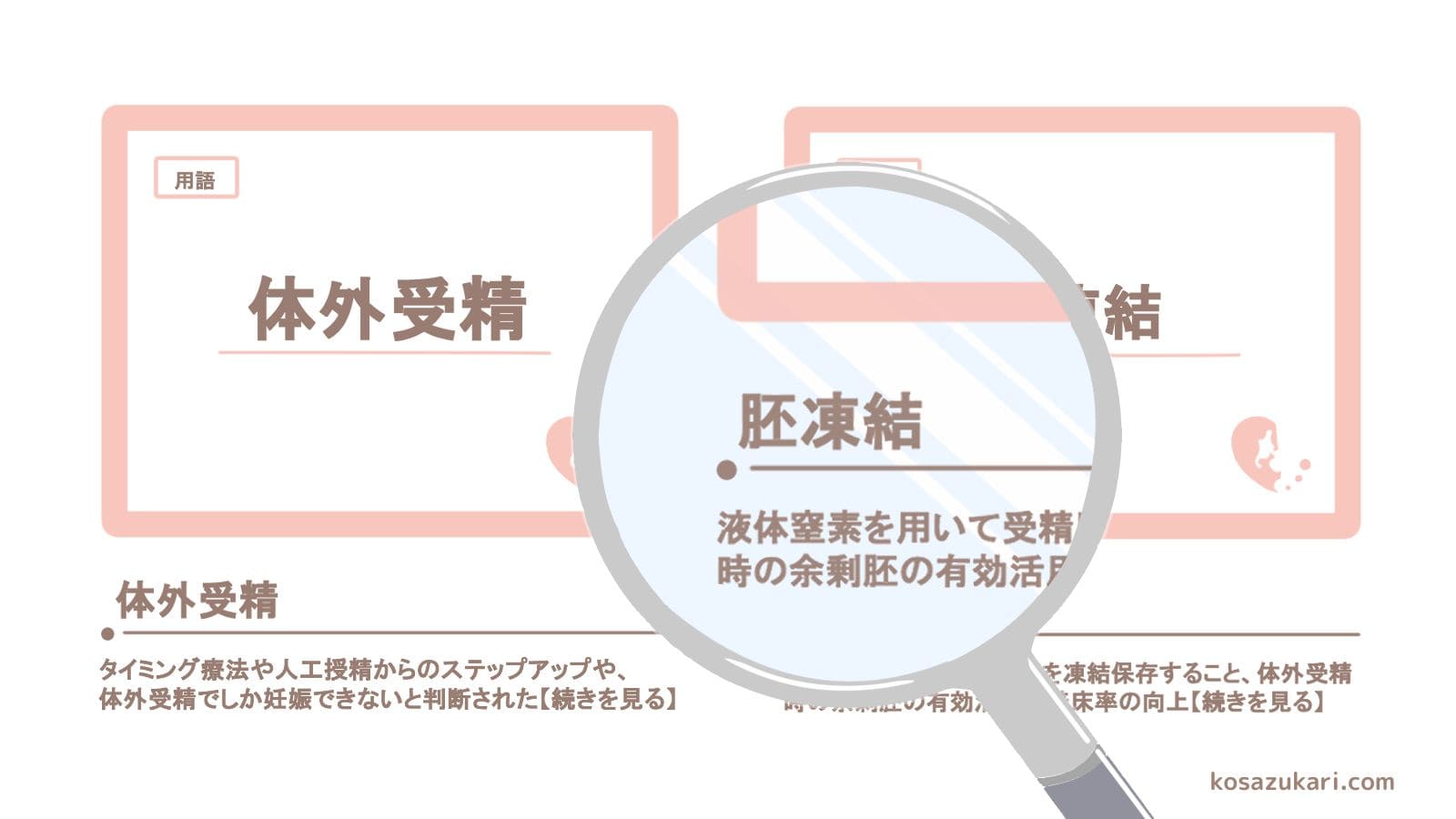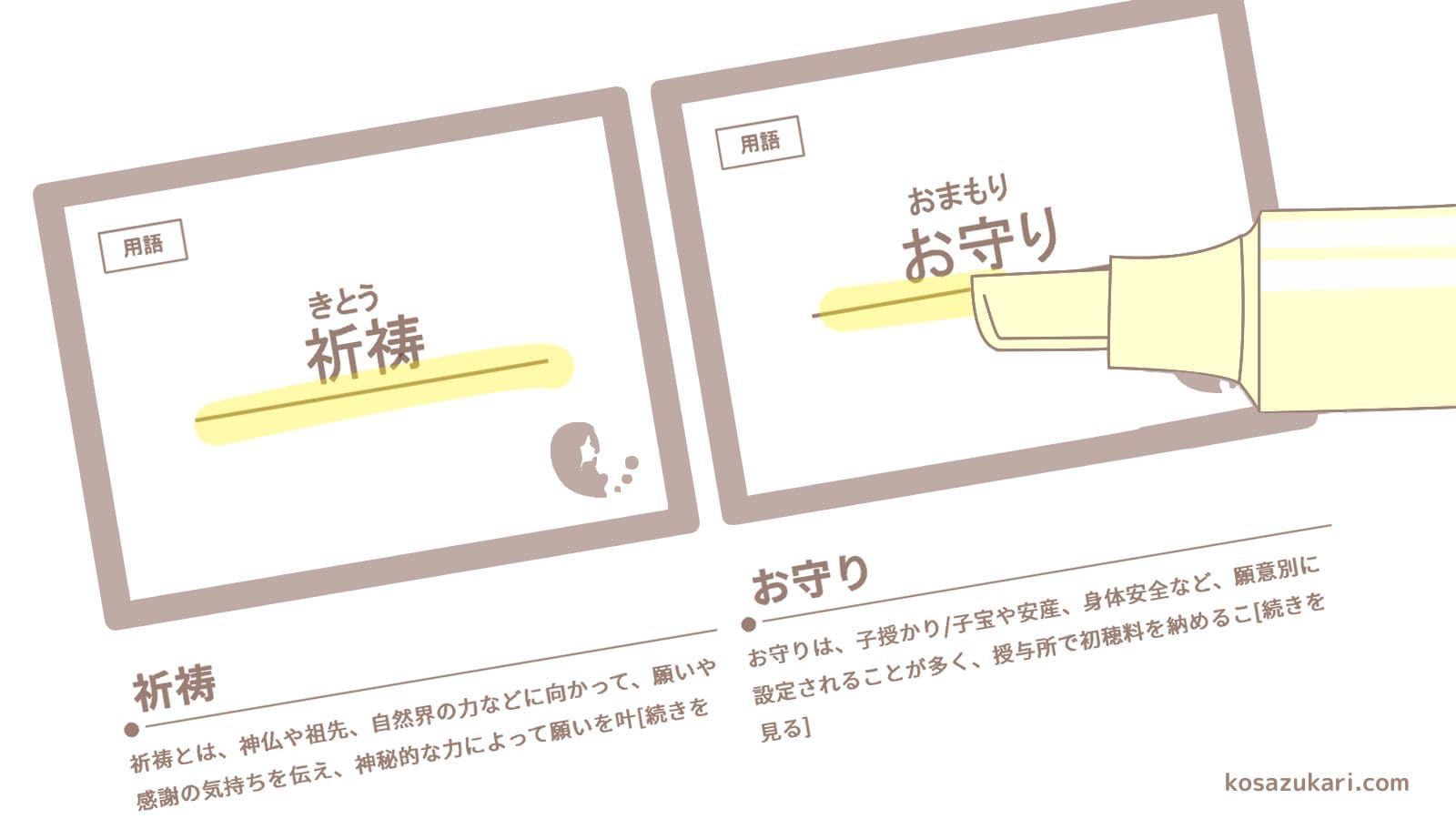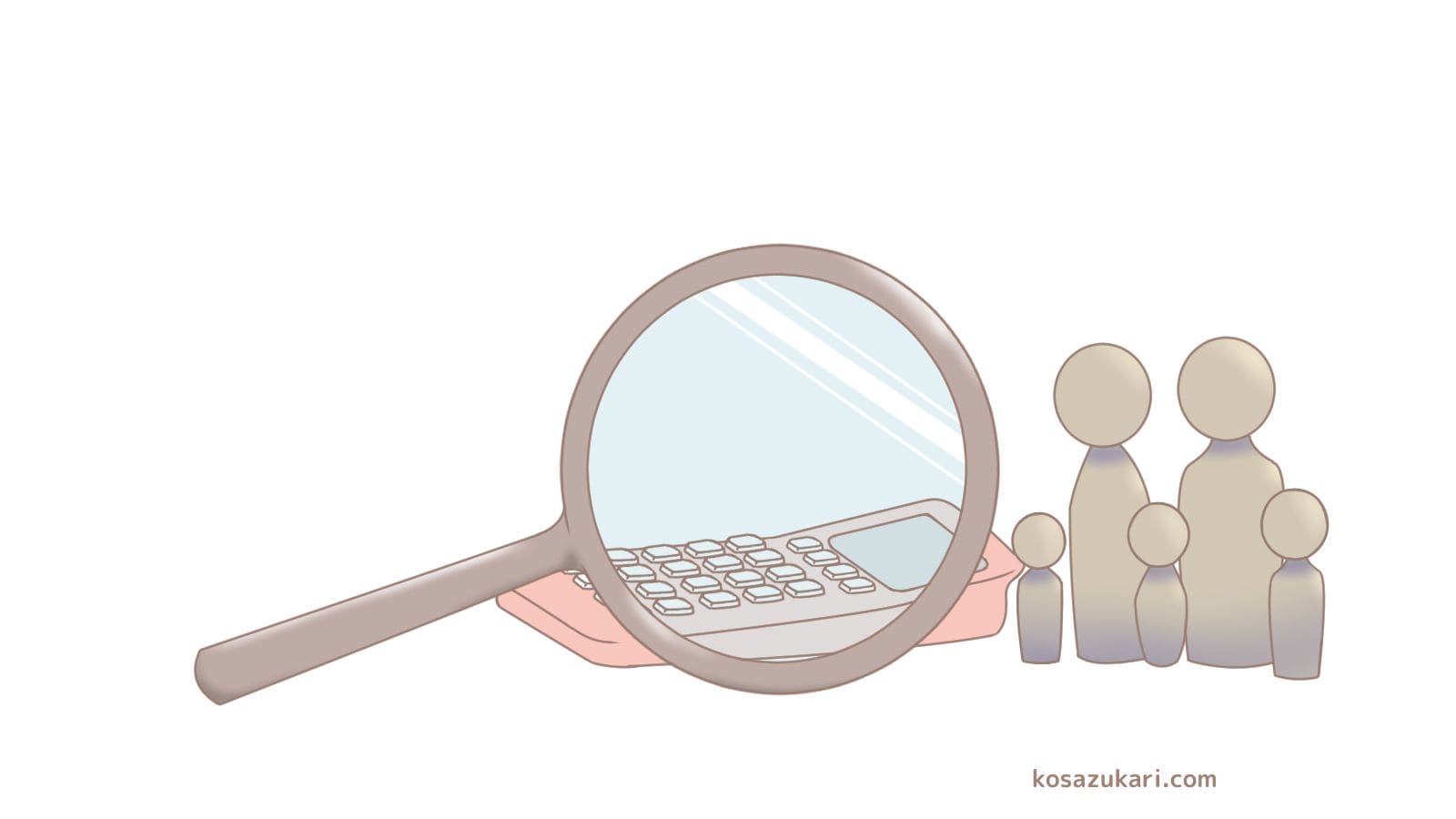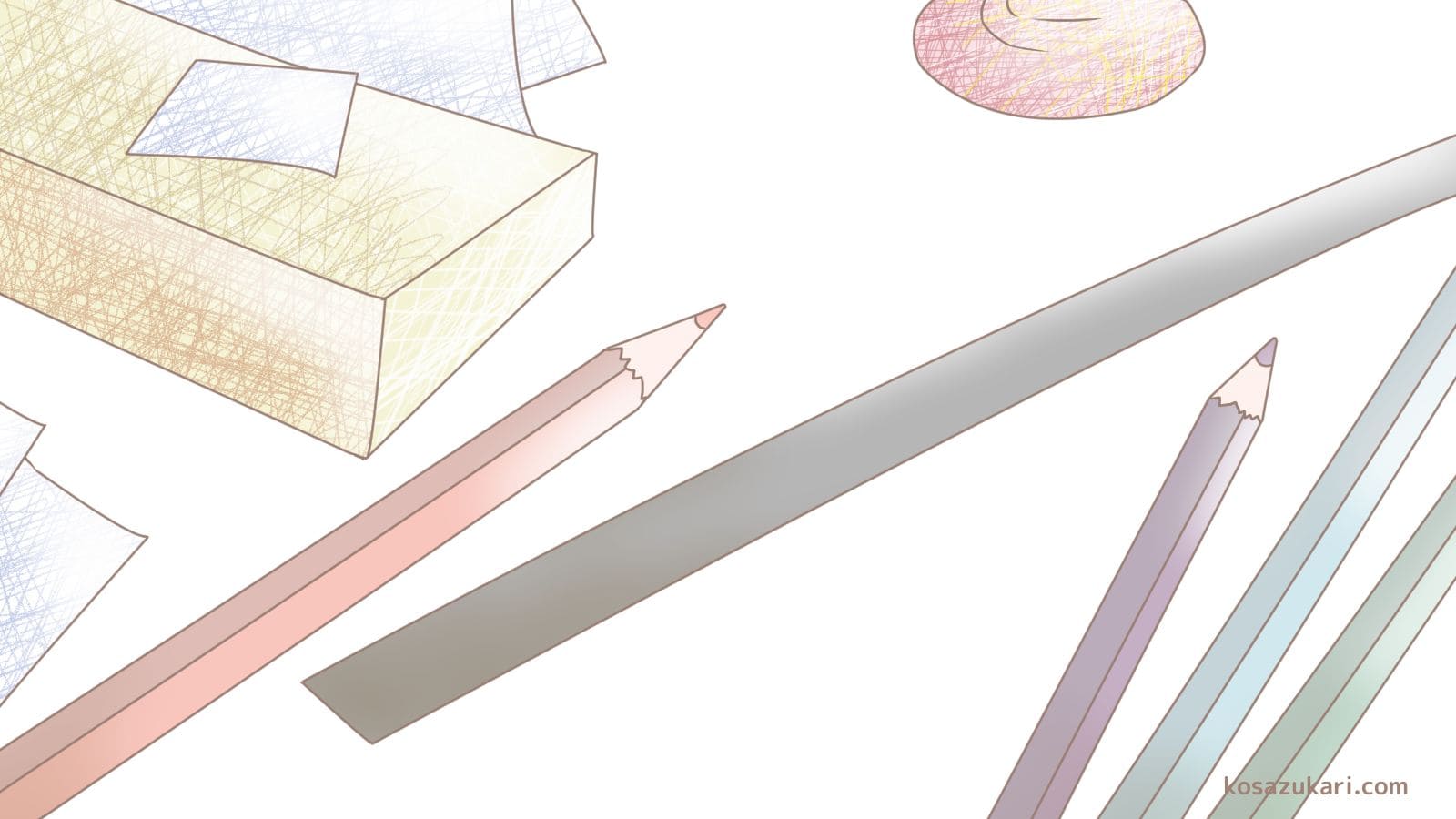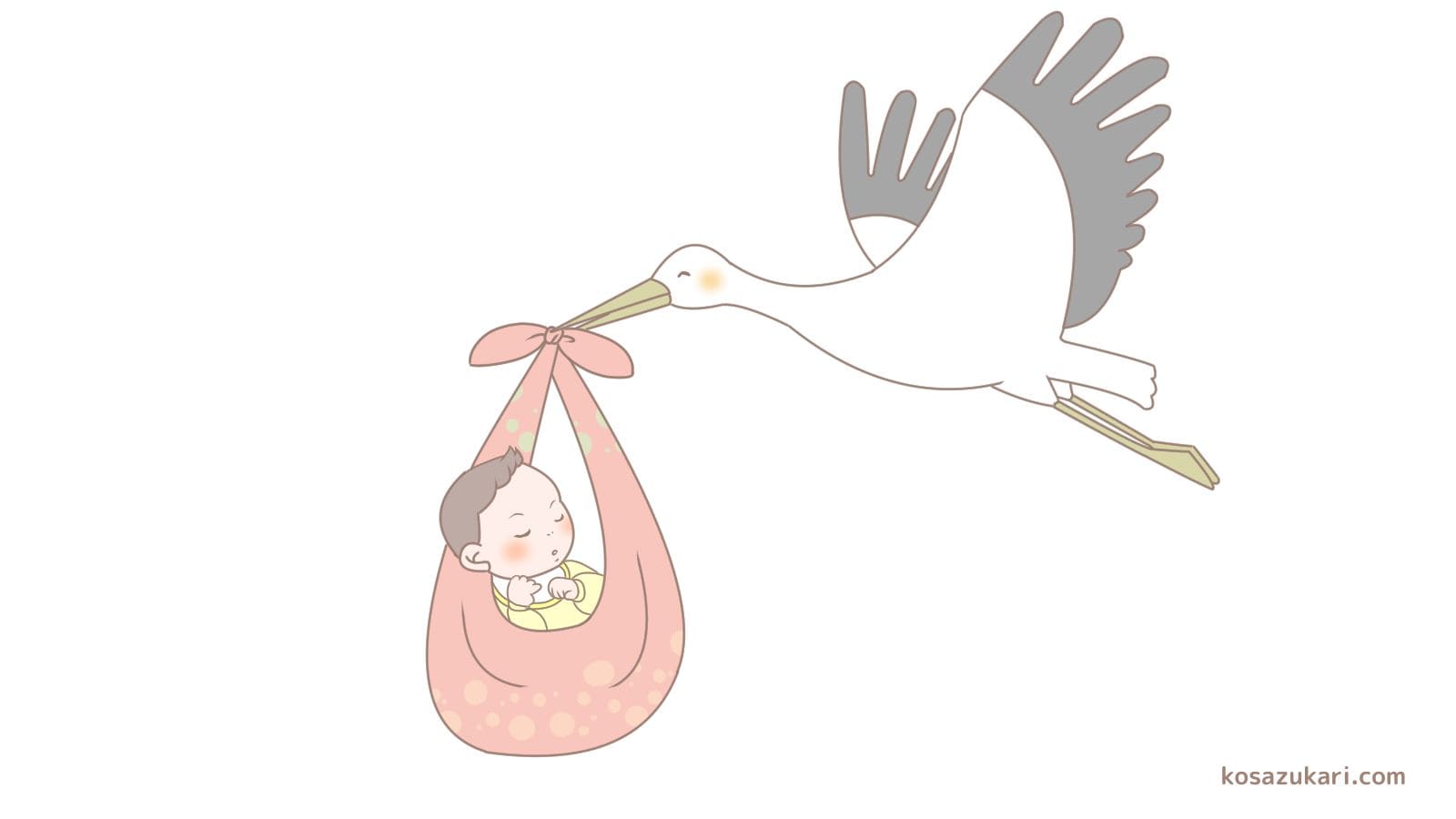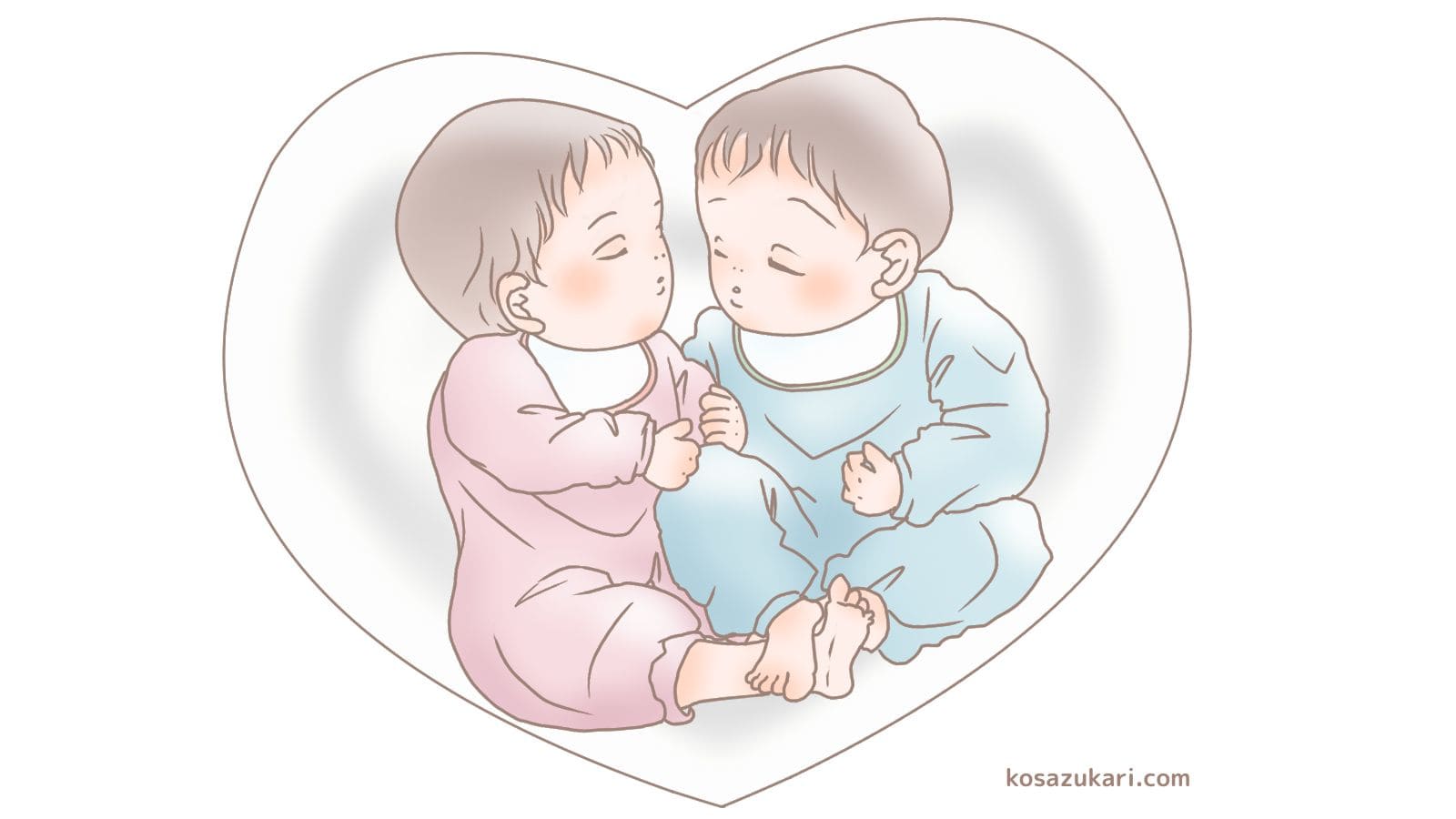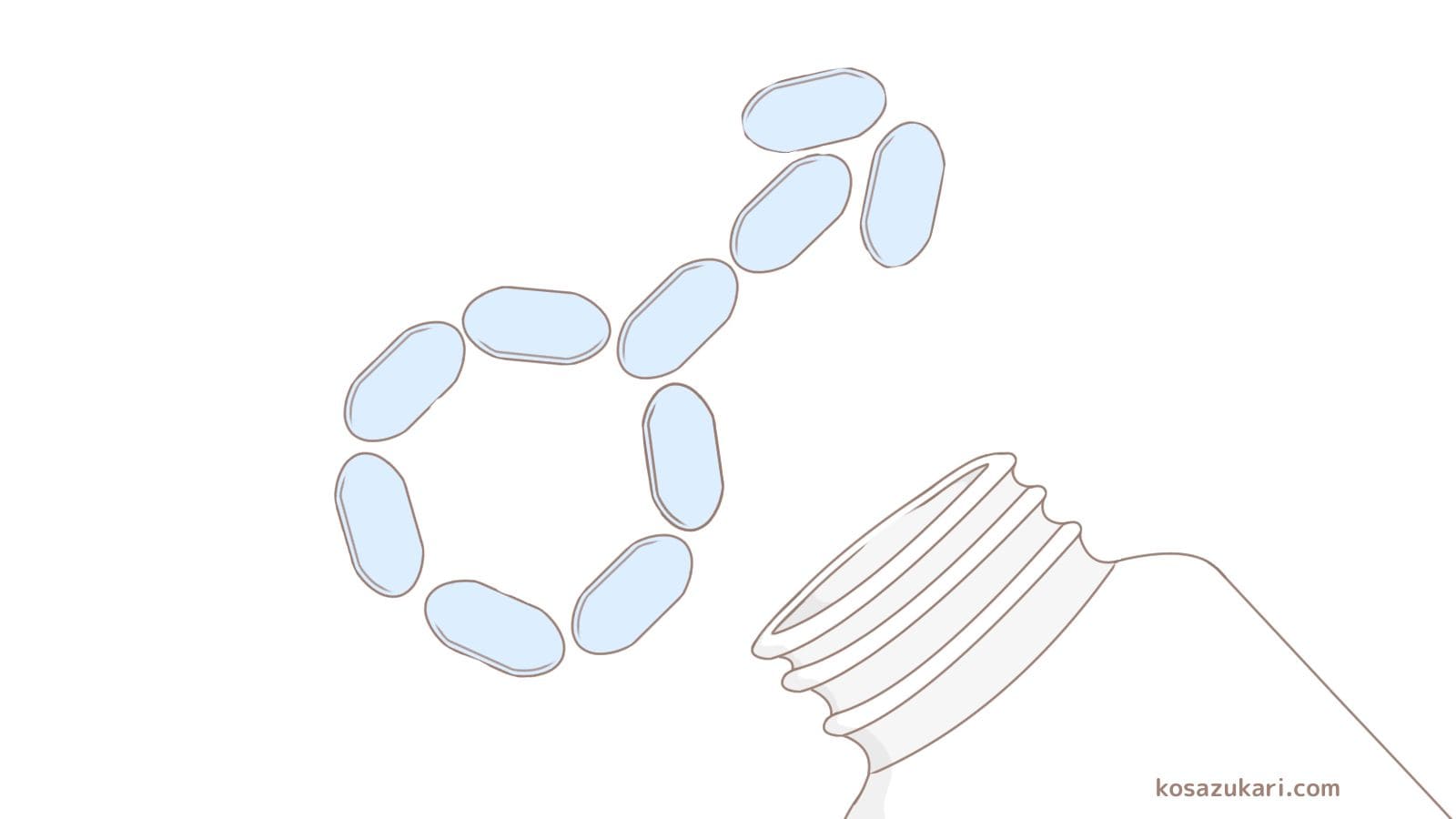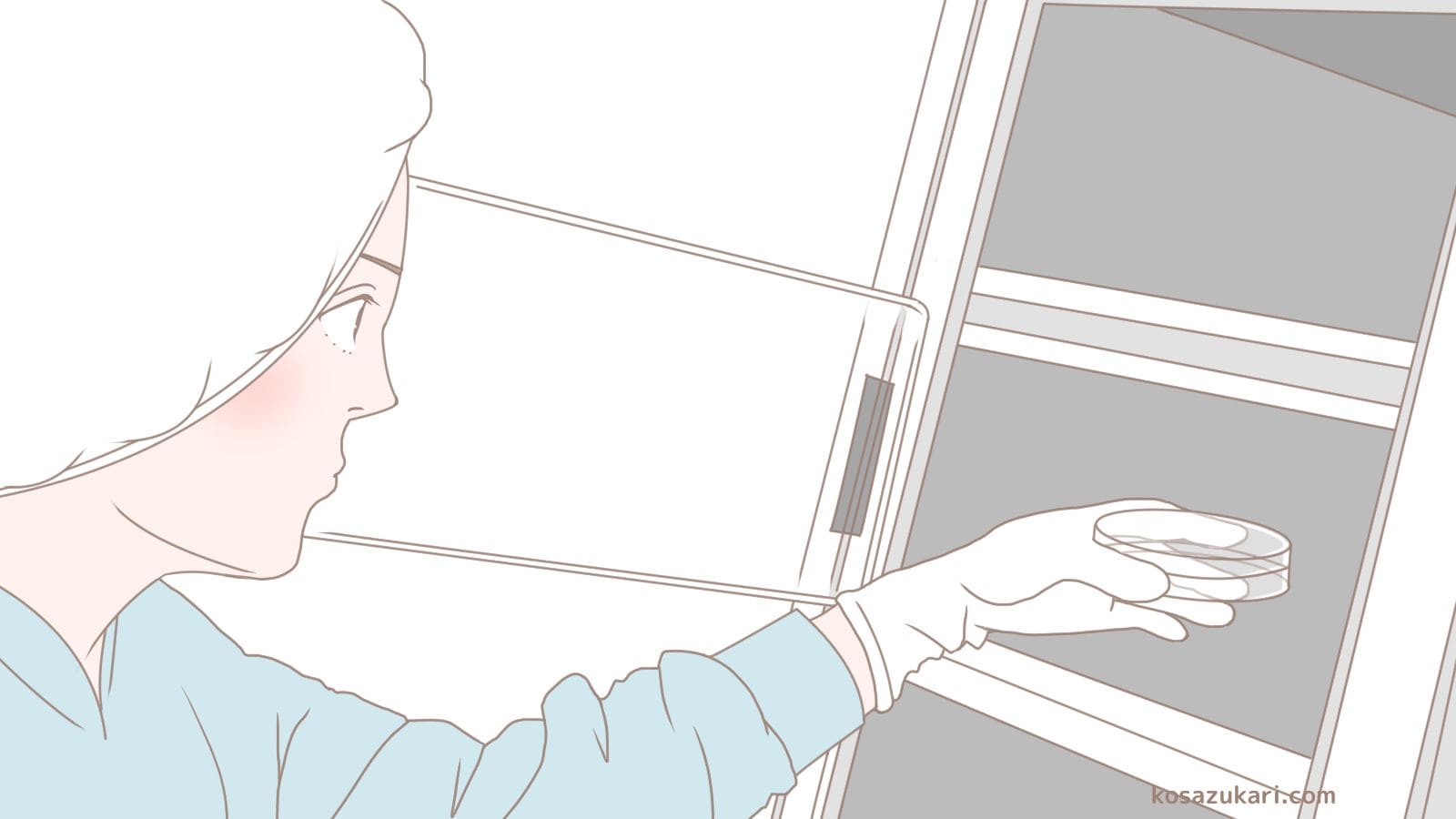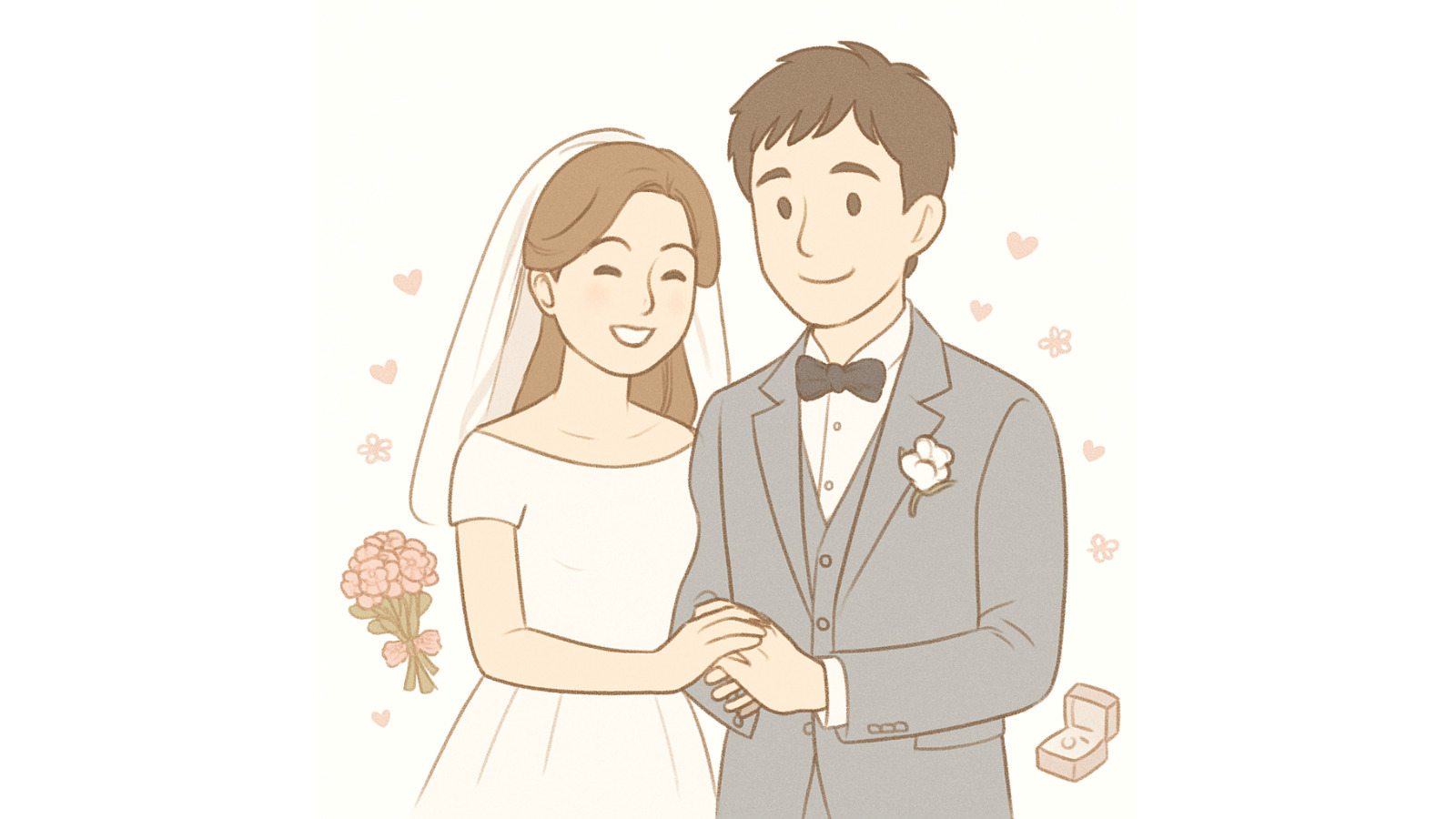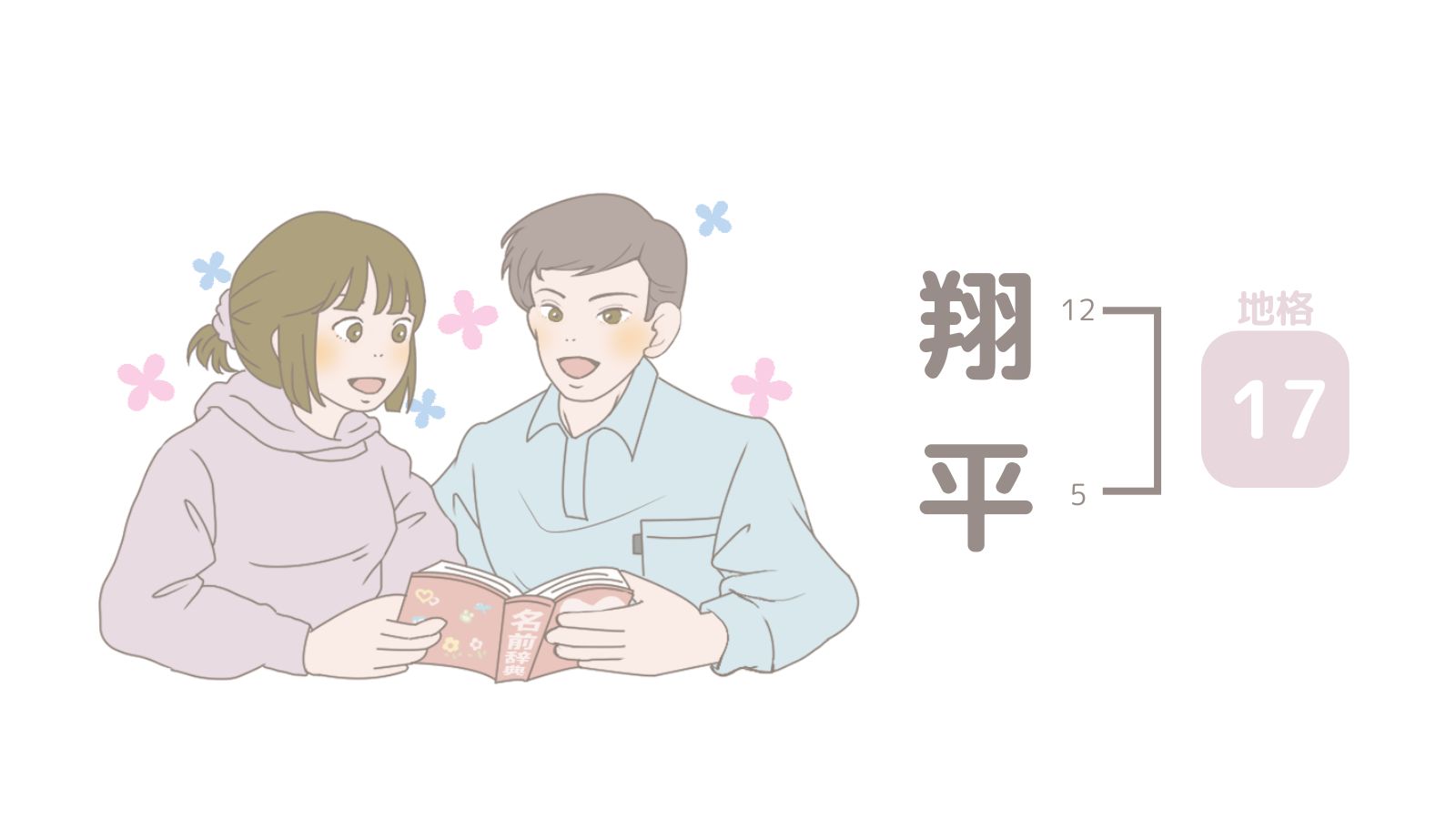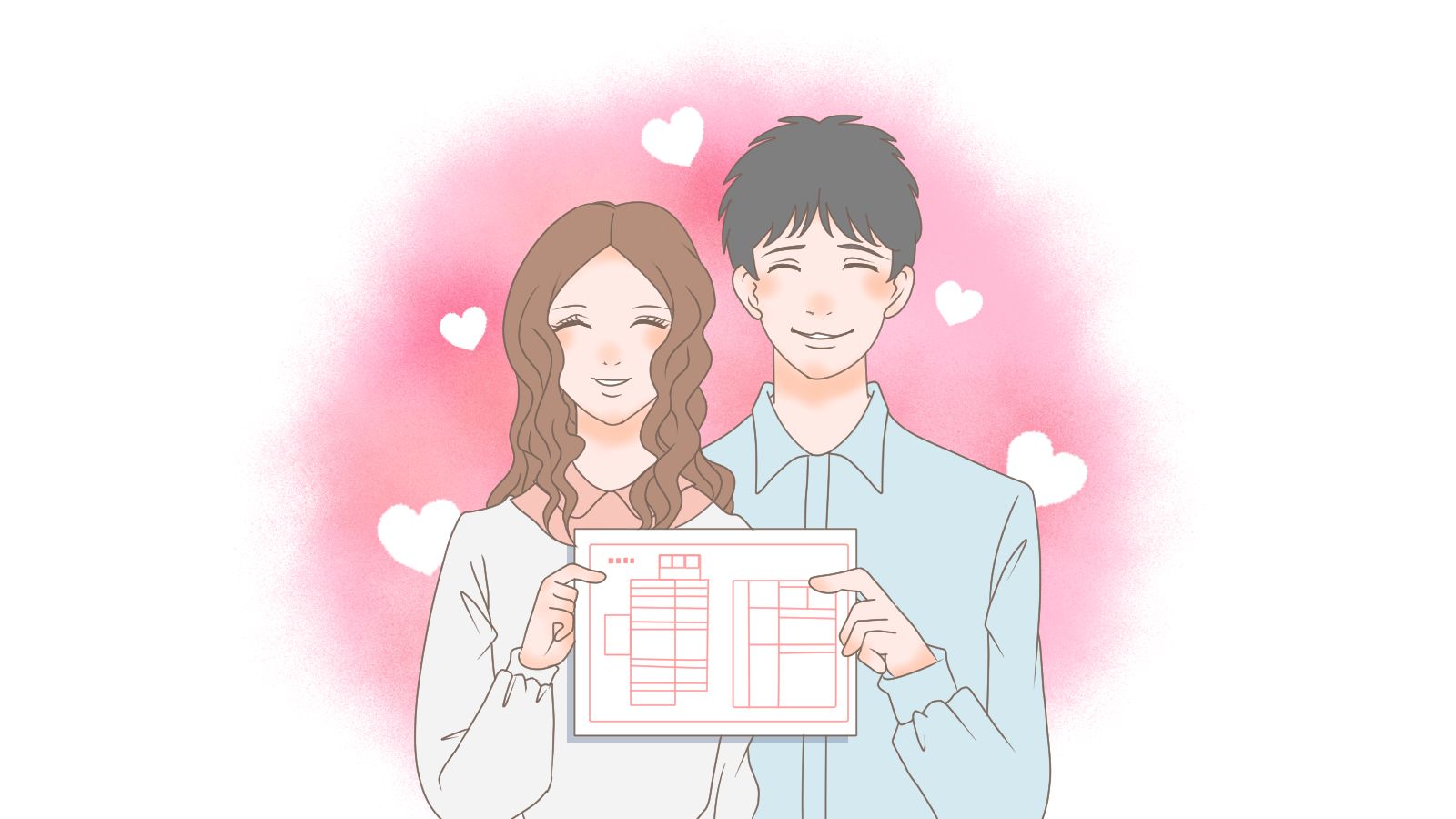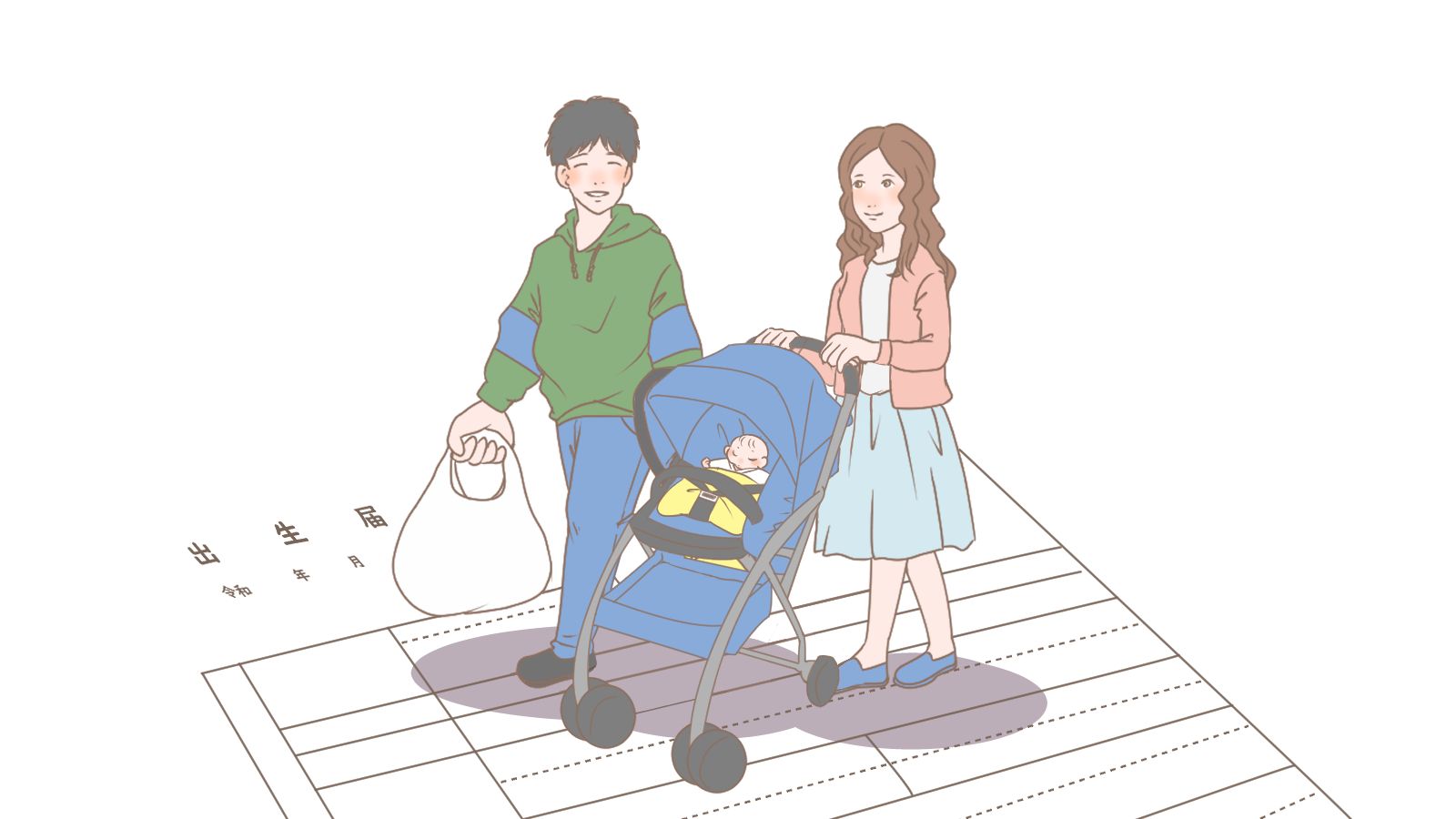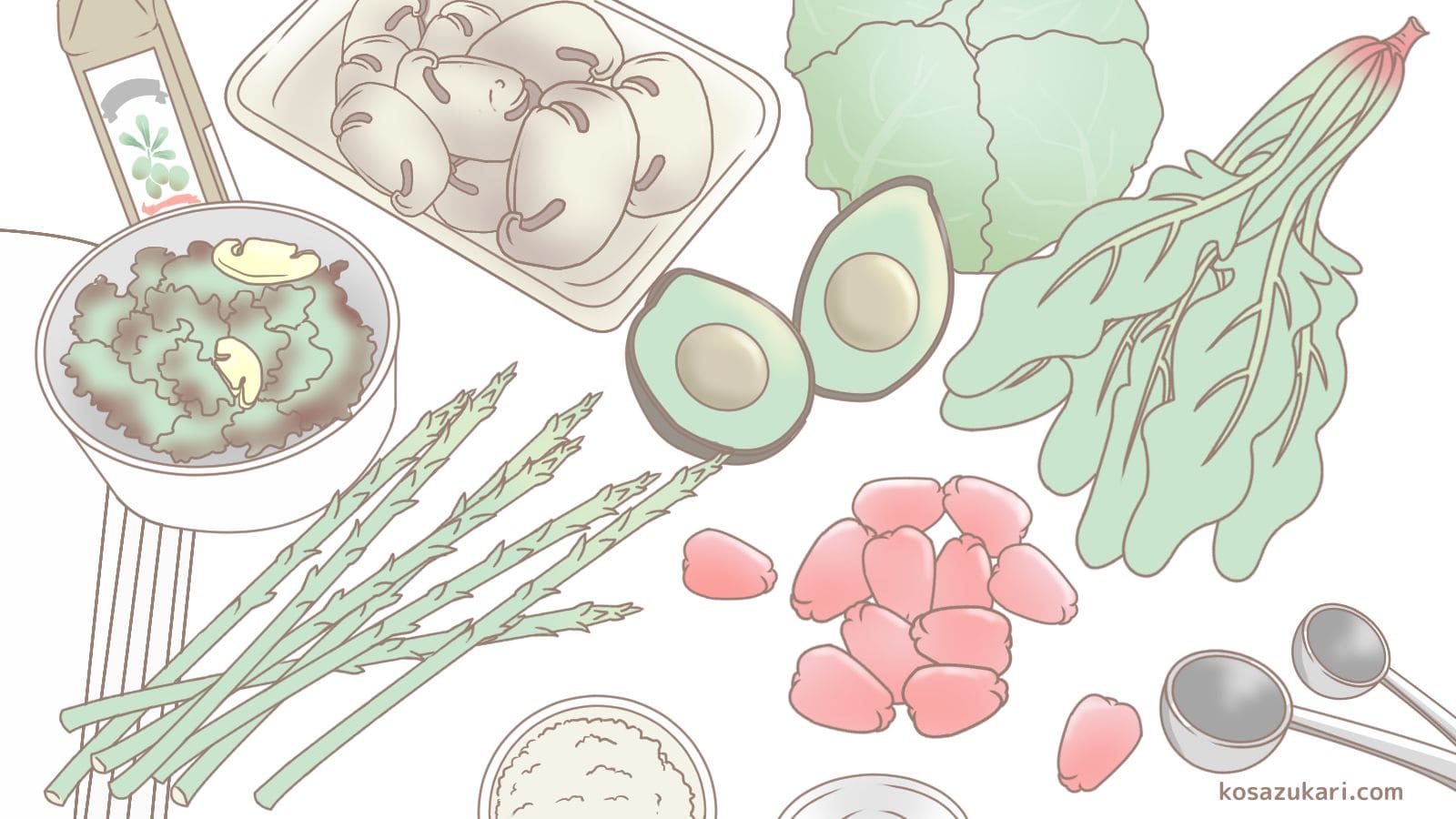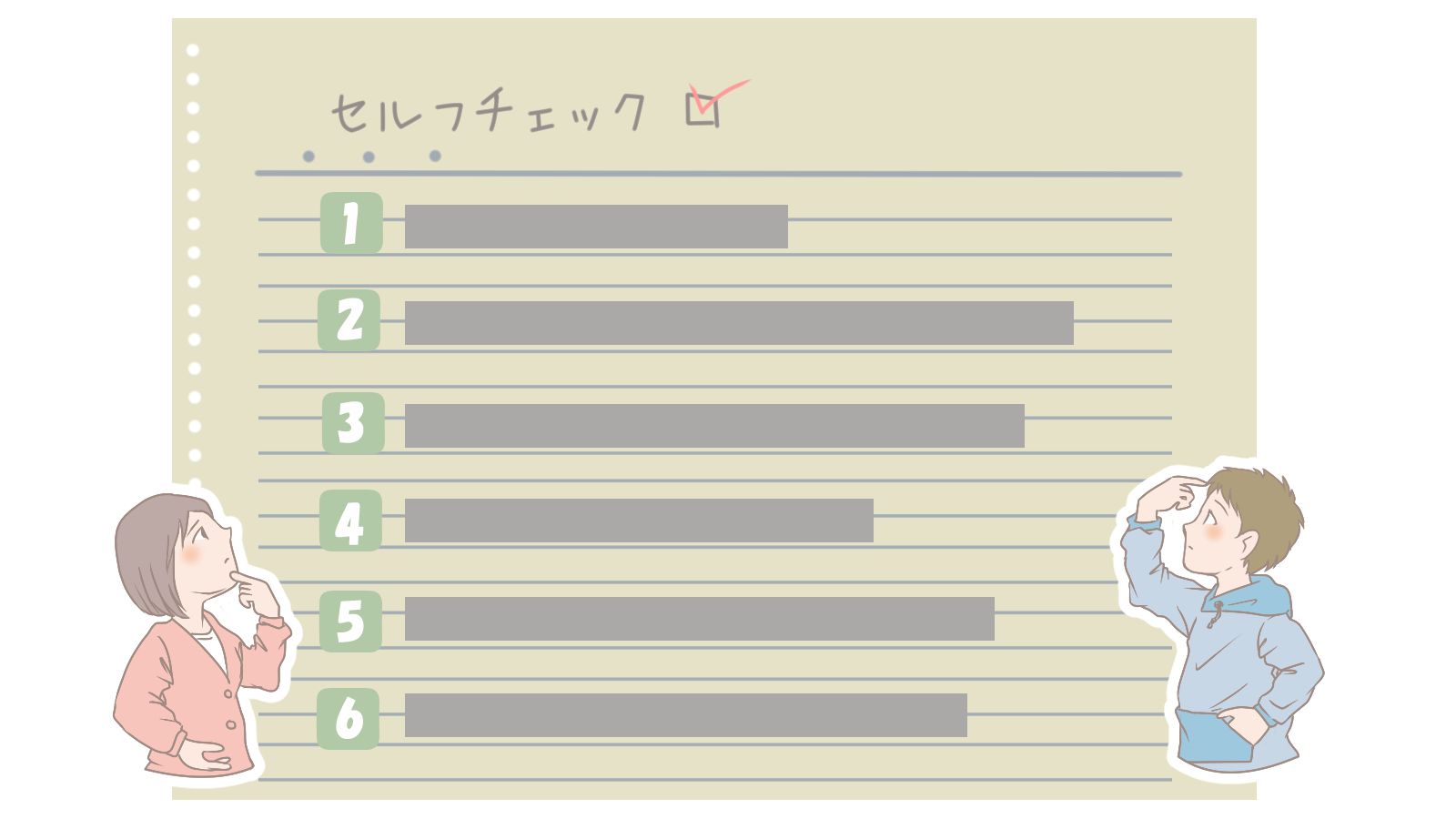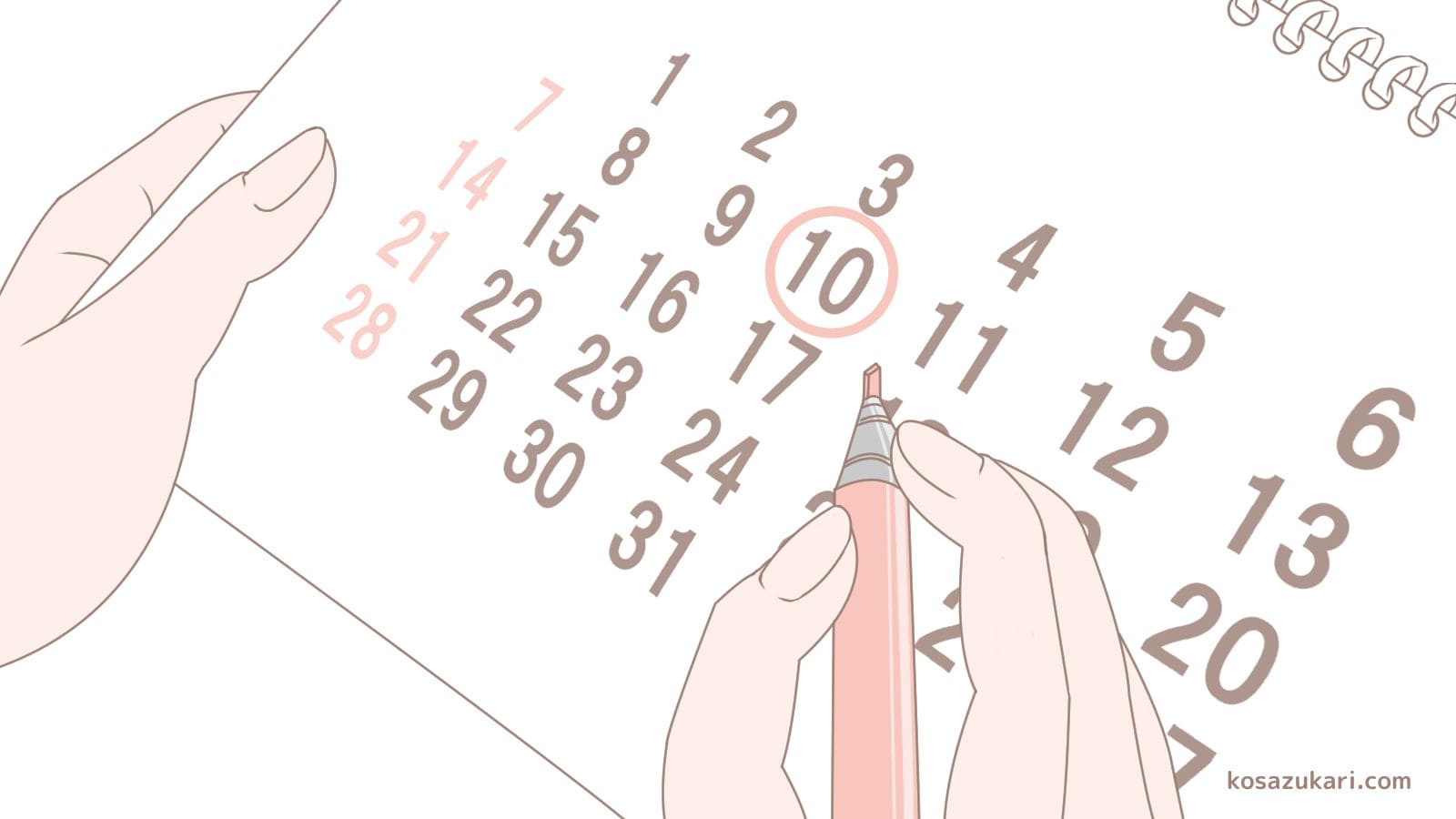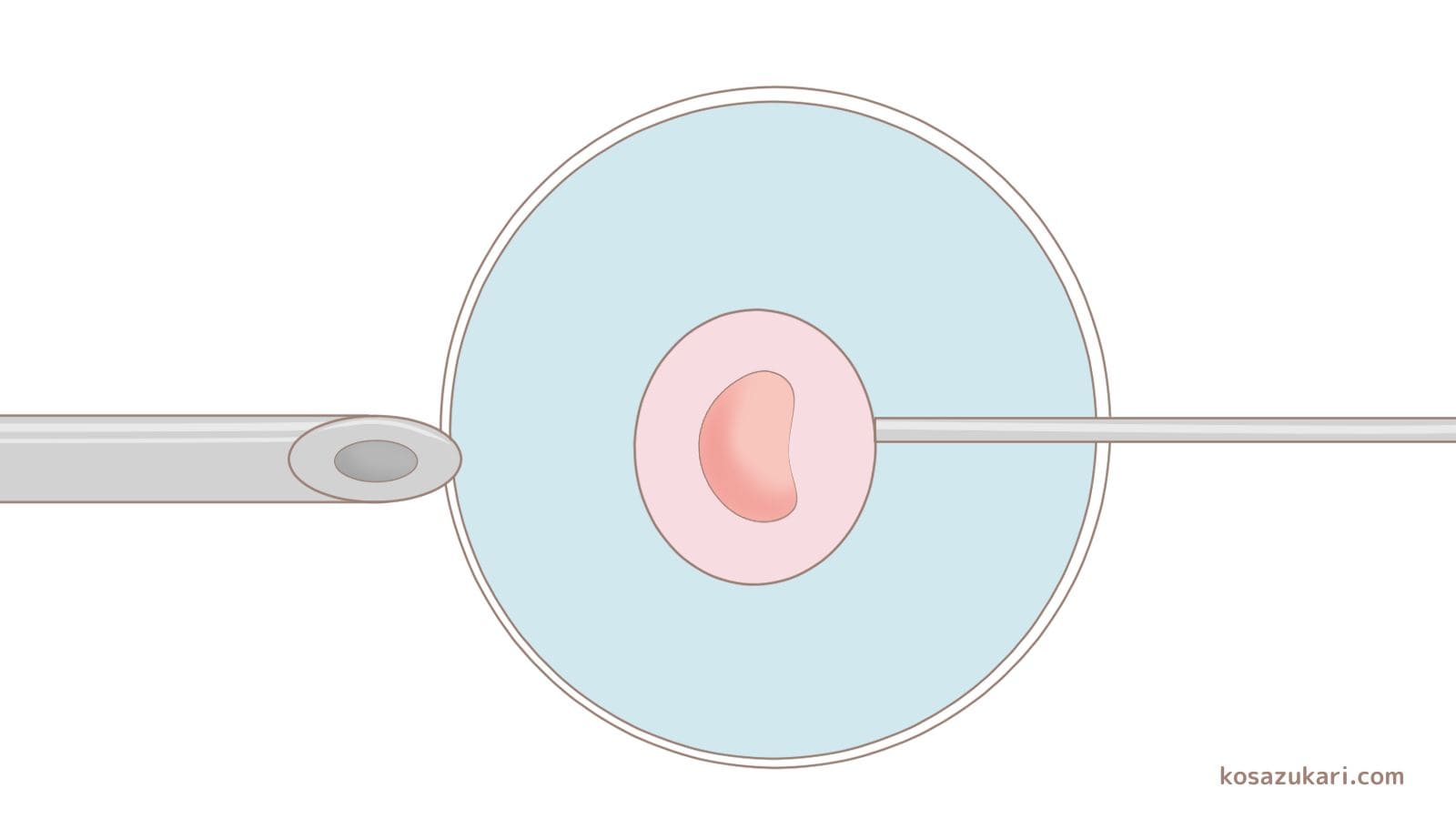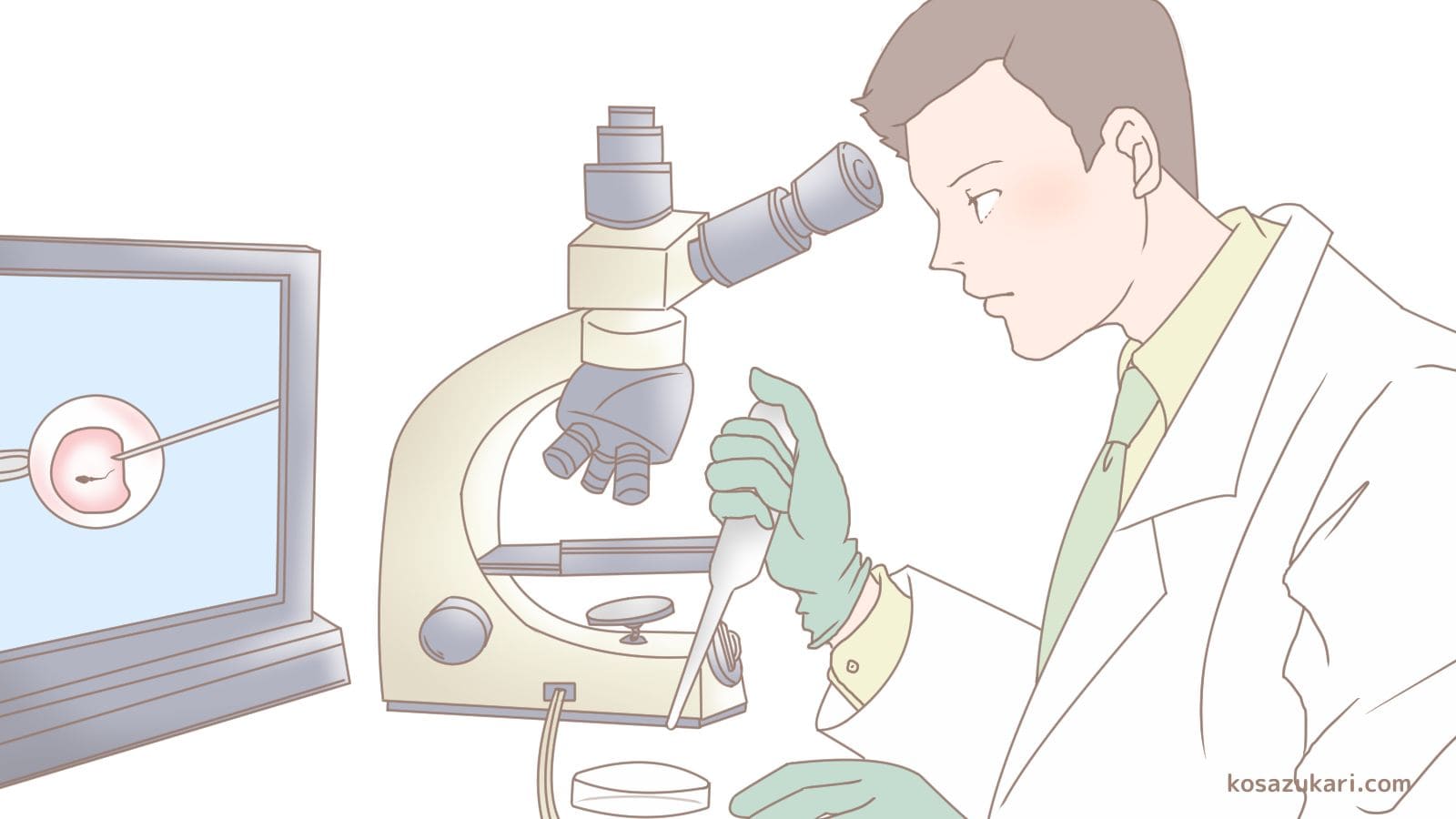卵管鏡下卵管形成術(FT)を受けた後、「どのくらいの確率で妊娠できるのか?」と気になる方は多いのではないでしょうか。調べてみても、妊娠率の数字が明確に書かれていないケースが多いです。そこで本記事では、その理由をわかりやすく紹介します。
さらに、術後の妊娠率を高めるために重要な“再閉塞リスクへの対処”や“生活習慣の見直し”についても触れています。この記事を読めば、「FTの妊娠率がどう変わるのか」という疑問がクリアになり、今後の治療計画を考えるうえでのヒントを得ていただければ幸いです。
FT(卵管鏡下卵管形成術)術後の妊娠率を左右する要因とは
FTは卵管の狭窄や閉塞を改善し、自然妊娠の可能性を再び高める治療法として注目されています。しかし実際には、卵管が通ったからといって必ずしも高い妊娠率が保証されるわけではありません。卵管以外にもさまざまな要因が絡み合い、トータルで妊娠率が決まってくるのです。ここでは、“FT術後の妊娠率”に影響する主なポイントを2つの観点から解説します。
卵管因子以外の不妊要因も関わる
- ・卵巣機能や男性不妊など、ほかの要因が大きく左右
FTによって卵管が通るようになっても、男性側の精子数・運動率、女性側の排卵力などによって妊娠率は大きく変動します。子宮内膜症・ホルモン異常などの複合要因も含めると、「卵管だけ」の問題ではないケースが多いです。 - ・FTだけで妊娠率を断定しづらい背景
卵管が開通しているかどうかは、不妊治療において重要なファクターですが、それ以外の因子がどの程度影響するかによって最終的な妊娠率は大きく変わります。加齢や卵巣機能の低下、男性不妊などを含め総合的に判断することが大切です。
ポイント:FT後に自然妊娠が期待できるかどうかは、「卵管の状態+α」の視点を持つことが欠かせません。いくら卵管が通っていても、他の要素が不十分なら妊娠率は高まらない可能性があります。
手術の成功度合いと再閉塞リスク
卵管鏡下卵管形成術(FT)を行っても、手術後の管理が十分でない場合や生活習慣が悪い状態が続くと、広げた卵管が再度狭くなる「再閉塞」が起きる可能性があります。癒着が再発すると妊娠率は再び低下するため、術後のケアがとても重要です。
また、成功度合いは閉塞部位の長さや癒着の程度に左右されます。軽度の狭窄ならカテーテルで通すのも容易ですが、長年の炎症などで卵管が大きく損傷しているケースでは、FTの効果が限定的になりがちです。
温活や生活習慣の改善でサポート
FT後の骨盤周りの血流を促進する“温活”を取り入れれば、再閉塞リスクを低減し、妊娠率を高められる可能性があります。食事の見直しや適度な運動、ストレス管理など、卵管と子宮環境を整えるライフスタイルを意識することも大切です。
ポイント:FTはあくまで“卵管を通す”ための治療であり、手術後のフォローやセルフケア次第で妊娠率が左右される面が大きいのです。

体外受精との比較
妊娠率の数値は個人差や複合要因によって大きく変わるため、一概に「FTを受ければ○%」というような明確な数字を提示しにくいのが現状です。そのため、本記事では年齢や卵巣機能、男性因子など多面的に見て体外受精(IVF)と比較しながら、治療選択の際の考え方を紹介します。
卵管因子を迂回できる体外受精
卵管が完全閉塞している場合でも、体外受精(IVF)なら卵管を通さずに受精を行うため、卵管の状態に関わらず妊娠を目指せます。一方で、体外受精は採卵や培養など費用や身体的負担が比較的高くなる場合があるため、年齢が若い方や卵管因子以外に大きな問題がない方は、まずFTを試すケースも少なくありません。
年齢が高い場合や複合的な要因が強い場合はIVFを優先
- ・40代以降で卵巣機能が低い、男性不妊や子宮内膜症が重度、などのケースでは時間をかけずに体外受精へステップアップしたほうが総合的な妊娠率が高い場合もあります。
- ・卵管を通す工程が必要になるFTでは、閉塞が重度な場合や年齢が高い場合には効果が限定的になるかもしれません。
費用・侵襲面での違い
- ・FTのほうが侵襲が低い可能性
体外受精では採卵や培養など手間と費用がかさむ一方、FTは手術のリスクや再閉塞リスクはあるものの、IVFほどの高度医療行為ではありません。保険適用や助成金などを考慮すれば、費用面でメリットがあるケースもあります。 - ・妊娠率だけにとらわれず総合判断を
費用・通院回数・身体的負担・年齢的な制約など、考慮すべき要素は多岐にわたります。「FTで卵管を通すメリット」と「体外受精に早期移行するメリット」を天秤にかけ、医師とともに適した治療法を考えることが大切です。
まとめ:FTは卵管因子による不妊に対して強力な選択肢ではあるものの、年齢やほかの不妊要因が絡むと妊娠率は大きく変わります。体外受精のほうが早い段階で結果を出せる場合も多いため、妊娠率の数字だけに振り回されず、総合的な治療プランを検討しましょう。

FT術後の妊娠率アップに向けた対策
FTによって卵管を広げても、それだけで妊娠率が大幅に上昇するわけではありません。術後の過ごし方や生活習慣、医療スタッフとの連携など、さまざまな要素が結果を左右します。ここでは、再閉塞リスクを軽減しながら妊娠率を高めるためのセルフケアや、もし妊娠に至らなかったときの次の選択肢を具体的に紹介します。
再閉塞予防のセルフケアと通院フォロー
FT後すぐにタイミングを取ったからといって、必ずしも妊娠率が上がるわけではありません。手術直後の卵管や子宮周辺に過度な刺激を与えると、かえって回復が遅れることも考えられます。医師の許可が下りるまで無理をせず過ごし、痛みや出血が続く場合は早めに受診するなど、術後のフォローを丁寧に行うことが大切です。
温活や生活習慣(栄養・運動・ストレス管理)で血流を維持
- ・温活:「腹巻きや半身浴」を取り入れ、骨盤周辺を冷やさないように心がけましょう。これによって卵管周りの血流が維持され、再癒着を防ぐ一助となる可能性があります。
- ・食事・運動:栄養バランスの良い食事や、ウォーキング・ヨガなどの適度な運動を行うことで、ホルモン環境を整えやすくなります。
- ・ストレス管理:日頃のストレスを放置しておくと、ホルモンバランスを乱しかねません。自分なりのリラックス方法を見つけ、定期的に気分転換を図ることも大切です。
1~2回の通院フォローで卵管の状態を確認
術後一定期間(おおよそ1~2週間程度)が経過したら、卵管が再度通っているかをクリニックなどで確認します。もし狭窄が進行していたり、新たな癒着が見られる場合には、追加のバルーン拡張や他の治療を検討することもあります。
ポイント:FT後は「手術が終わってひと安心」と思いがちですが、術後こそ医師の指示に従ってフォローアップを続けることが妊娠率アップのカギです。生活習慣を整えることでよりスムーズに回復し、再閉塞のリスクを最小限に抑えられるでしょう。
人工授精・体外受精へのステップアップ
FTを行っても妊娠に至らなかった場合、人工授精や体外受精(IVF)のような高度生殖医療にステップアップするタイミングを考える必要があります。たとえば、卵管の通過性が回復しても、男性不妊や排卵障害、子宮内膜症など他の不妊要因が強いと自然妊娠は難しい場合があるため、数カ月〜半年ほどタイミング法や人工授精を試しても結果が出ないなら、ステップアップを検討するのが一般的です。
特に35歳を過ぎると妊娠率が低下しやすく、40代に入るとさらに難しくなることが多いです。時間的猶予が少ないと感じたら、早めに体外受精へ移行するなどの方針を取るのも、後悔を残さない選択といえます。また、不妊治療では医師だけでなく、胚培養士・カウンセラー・栄養士などの専門家が連携し、それぞれの視点から支援してくれる場合があります。多職種のサポートを得ながら、適した治療プランや生活改善策を見つけるとスムーズでしょう。
ポイント:FTの効果を最大限に生かすには、「一定期間で妊娠しなければ次の治療に移行する」という判断が不可欠です。年齢や卵巣機能を踏まえつつ、医師や他の専門家と相談しながらベストな選択肢を組み立てていきましょう。

よくある質問(Q&A)
FT(卵管鏡下卵管形成術)については、「実際にどれくらいの期間で妊娠できるのか」「再度卵管が詰まってしまったらどうすればいいのか」といった具体的な疑問を多くいただきます。そこで、よくある質問をピックアップし、わかりやすくお答えしていきます。ご自身の状況と照らし合わせながら、治療の参考にしてみてください。
Q1.「FT後すぐに妊娠する人もいる?平均どれくらい?」
個人差は非常に大きく、卵管が通ったからといって術後すぐに妊娠が成立するわけではありません。卵巣機能や男性因子、ホルモンバランスなど他の要素も大きく影響します。若年層や狭窄が軽度だった場合には術後1〜2周期で妊娠できた例も報告されていますが、年齢が高かったり複合的な不妊要因がある場合は妊娠までに時間を要するケースが多いです。
妊娠への期待から心理的なプレッシャーが増すと、ストレスがホルモンに影響を与えてしまい、かえって妊娠を遠ざける可能性もあります。あくまでも目安として考え、医師と相談しながら冷静に進めることが大切です。
ポイント:早い人だと術後1〜2周期で妊娠する場合もありますが、半年以上かかるケースも珍しくありません。焦らず日頃の生活習慣やタイミング法を意識しながら、心身の負担をコントロールしていきましょう。
Q2.「再度閉塞した場合、FTをもう一度受けられる?」
二度目のFTが可能かどうかは、卵管の損傷度や癒着の程度によって異なります。再度バルーンカテーテルで狭窄を拡張できる例もありますが、一度手術を受けている分、卵管や周辺組織にさらなるダメージを与える恐れもあるため、慎重に判断する必要があります。
また、何度も卵管を処置するより、体外受精(IVF)などの高度治療へ早めに進むほうが結果的に妊娠に近づきやすいと医師が判断する場合もあります。特に年齢が高い方や複合的な不妊原因を抱えている方は、担当医とよく相談しながら次のステップを決めることが重要です。
ポイント:二度目のFTか、体外受精へ進むかは「卵管の状態」「年齢」「不妊期間」「他の因子」などを総合的に考慮し、リスクとリターンを比較して決定します。繰り返しの手術による負荷と体外受精の費用・身体的負担を比べ、ベストな治療法を検討しましょう。
まとめ・結論
FT(卵管鏡下卵管形成術)の術後妊娠率は、卵管因子以外(年齢・卵巣機能・男性不妊など)の要素が大きく絡むため、個人差が大きいのが実情です。本記事では他サイトにはあまりない切り口として、年齢×卵管状態別の妊娠率目安表を提示しましたが、学会報告やクリニックの実例などを総合すると、術後の平均妊娠率は約10~40%程度とかなり幅があります。
「FTを受ければ誰でもすぐに妊娠できるわけではない」のはもちろんですが、狭窄・閉塞を取り除くことで自然妊娠のチャンスを取り戻せる可能性が充分にあるのも事実です。ただし、再閉塞を防ぐ術後ケアや、どのタイミングで人工授精・体外受精へ移行するかといった判断も重要となります。
あなた自身の状態(年齢、卵巣機能、不妊期間、男性因子など)を踏まえ、治療計画をしっかり立てることで、FTの効果を最大限に引き出すことが期待できます。気になる方は、ぜひ信頼できる専門医やクリニックでカウンセリングを受け、具体的な妊娠率の見通しを一緒に確認してみてください。
参考)
・日本生殖医学会 Q4.不妊症の原因にはどういうものがありますか?
・慶應義塾大学医学部 卵管鏡下卵管形成法の適応拡大に関する技術的検討および妊娠予後に関する検討