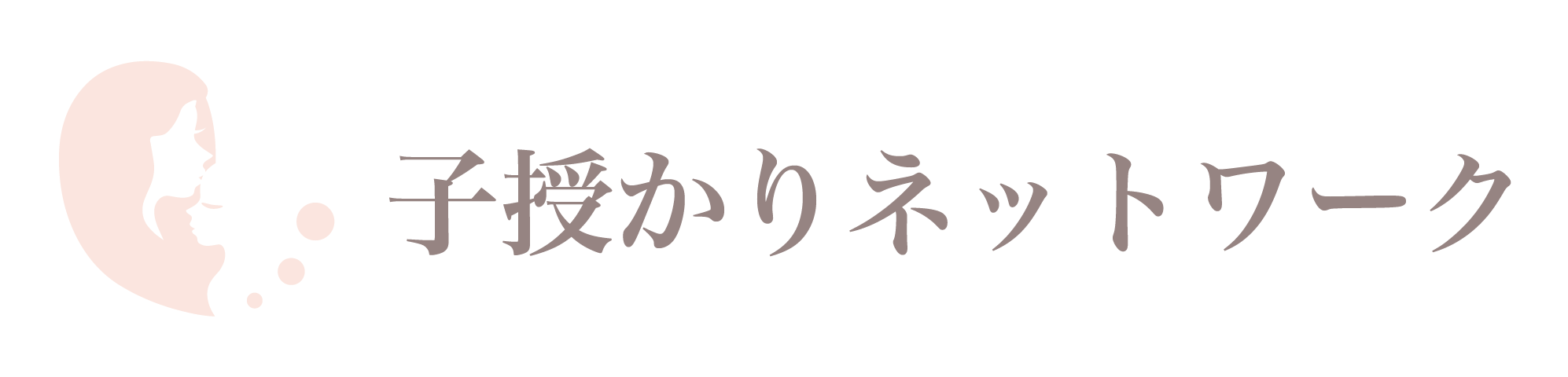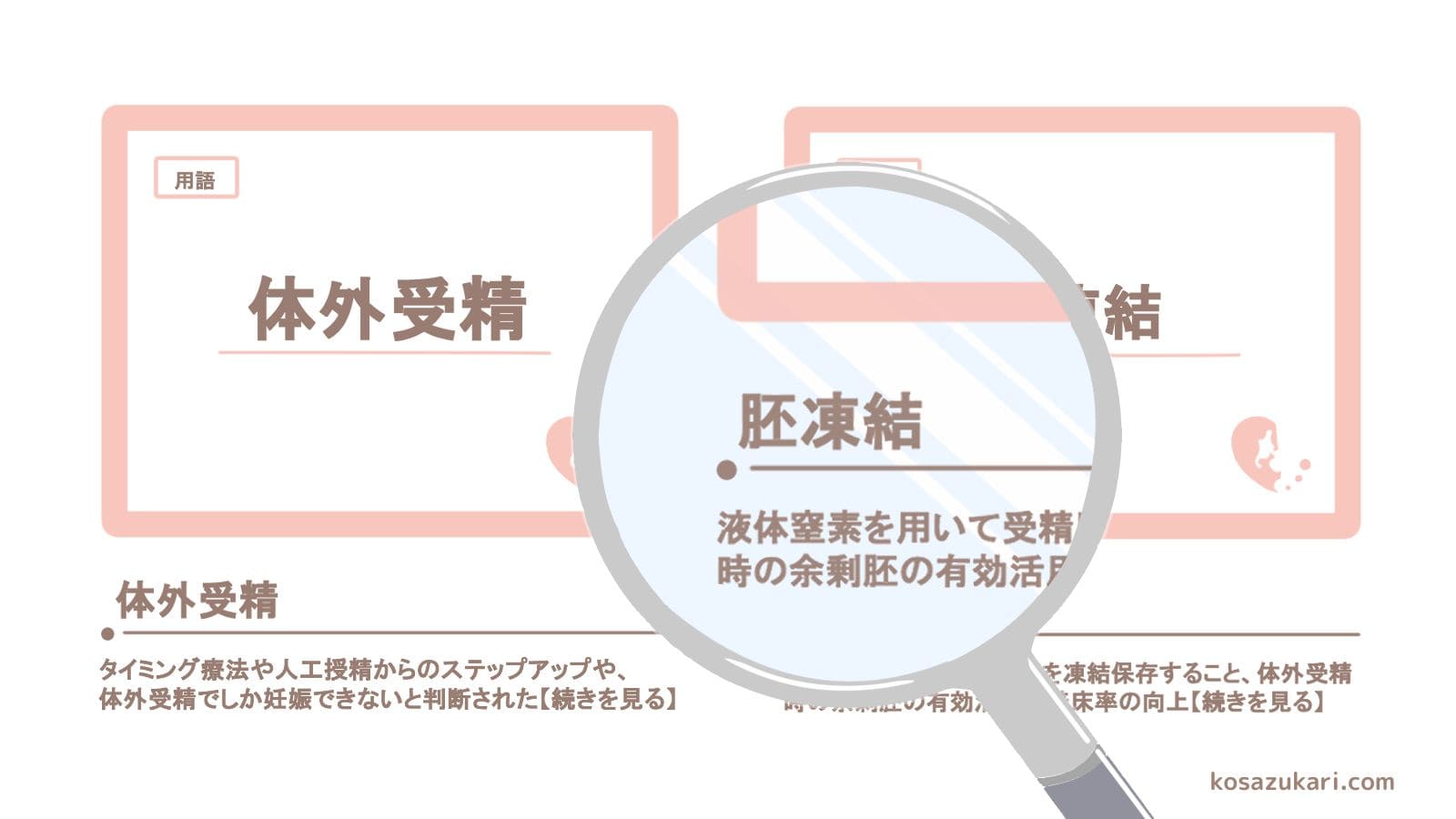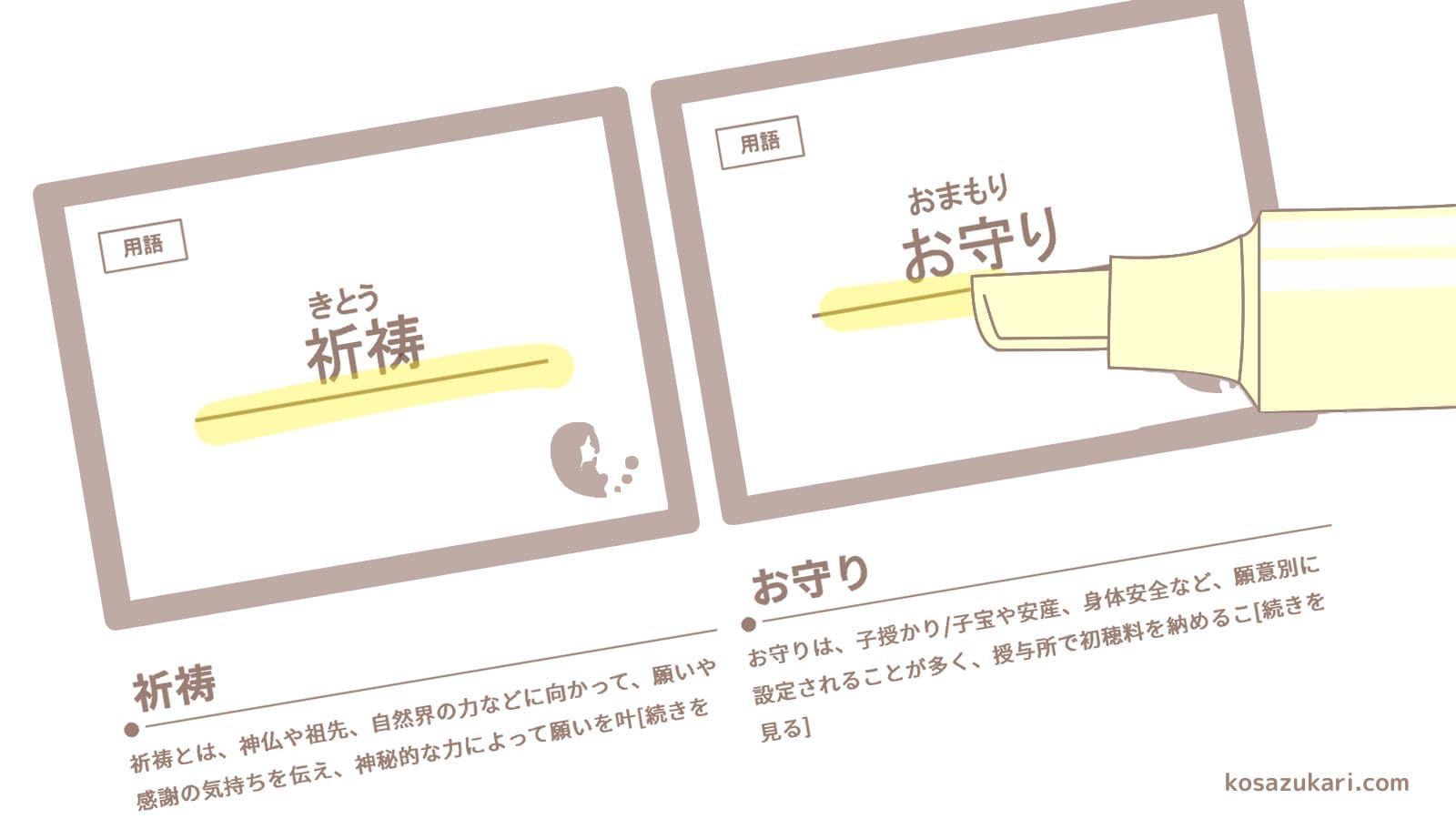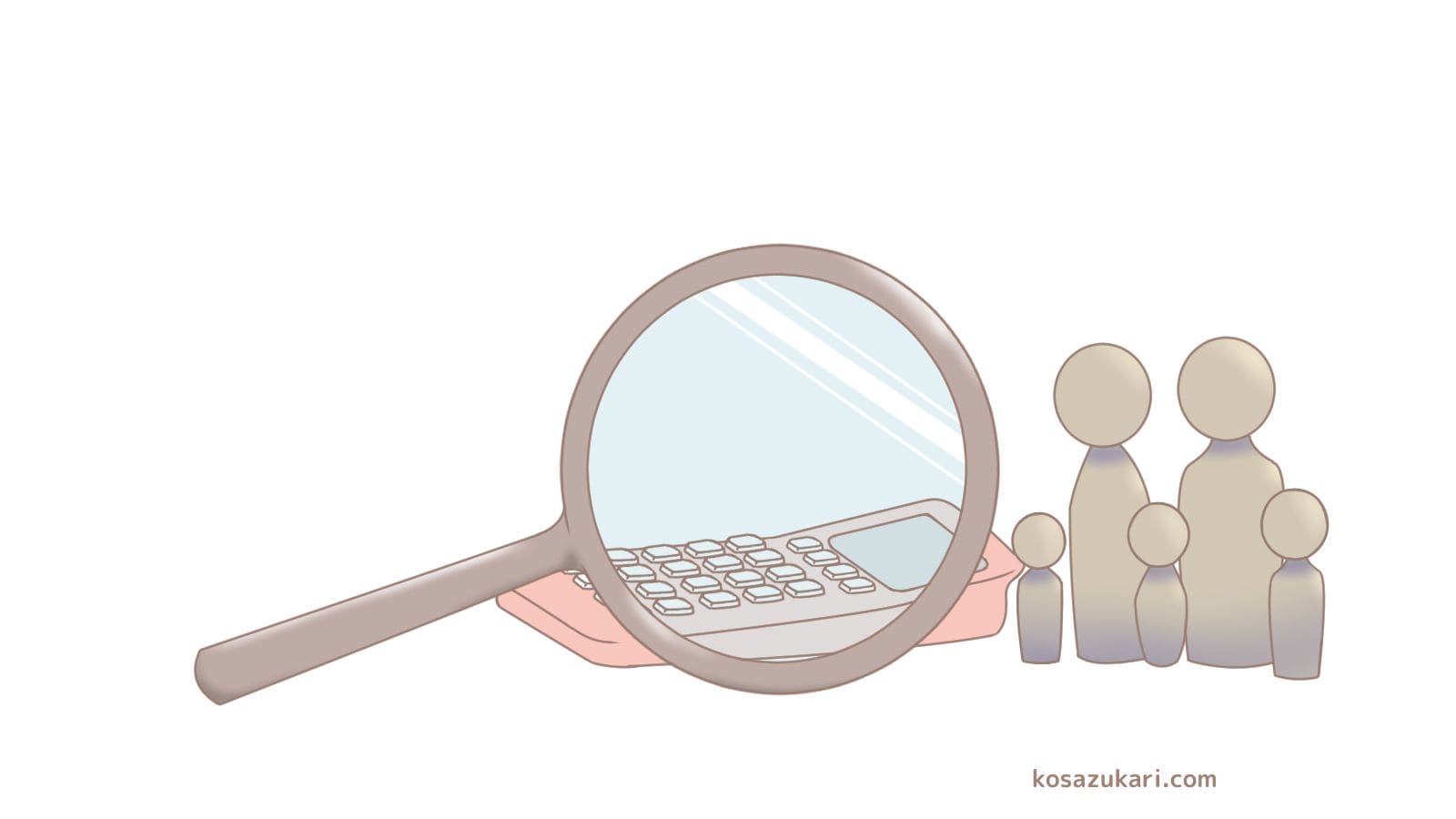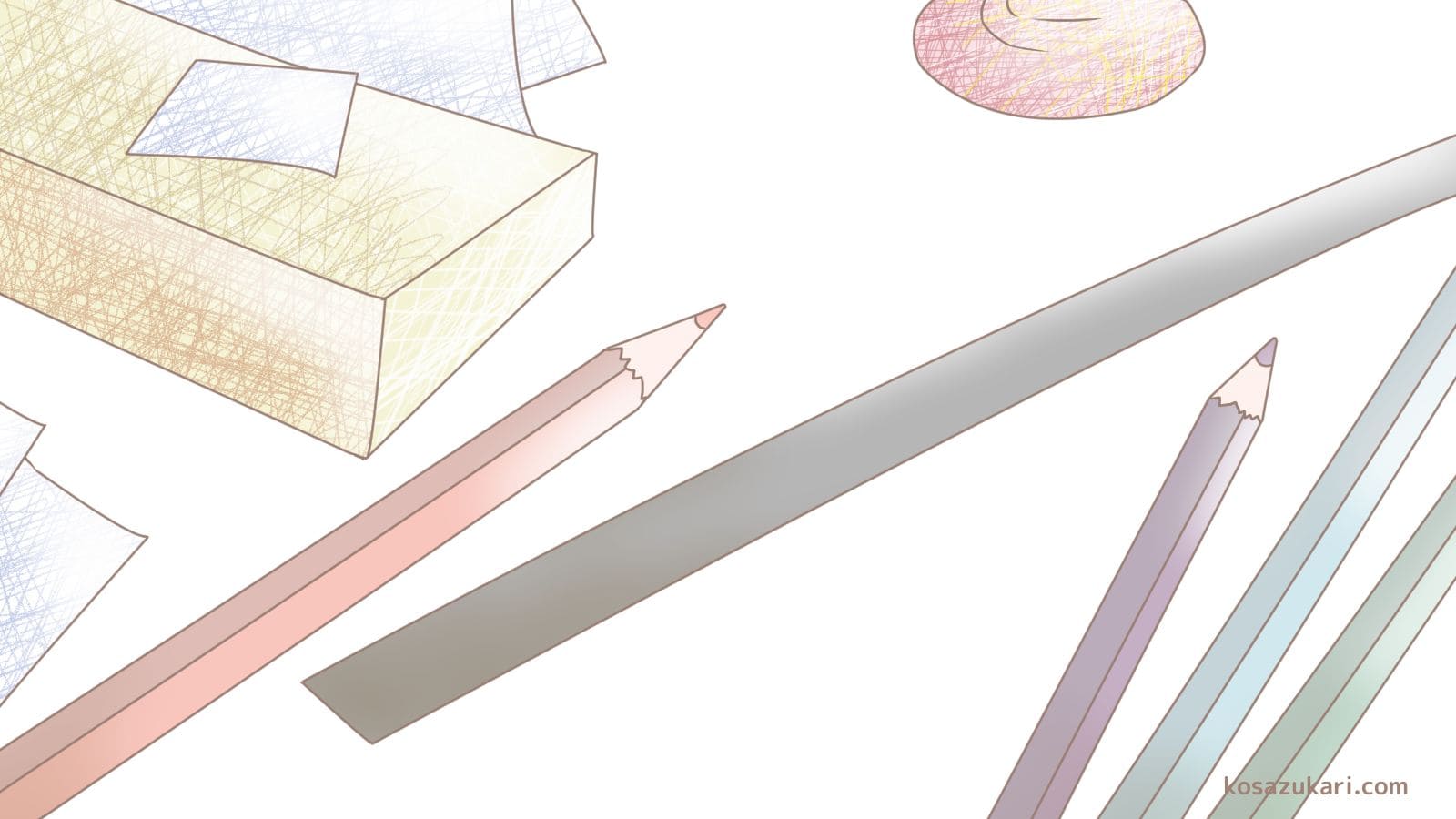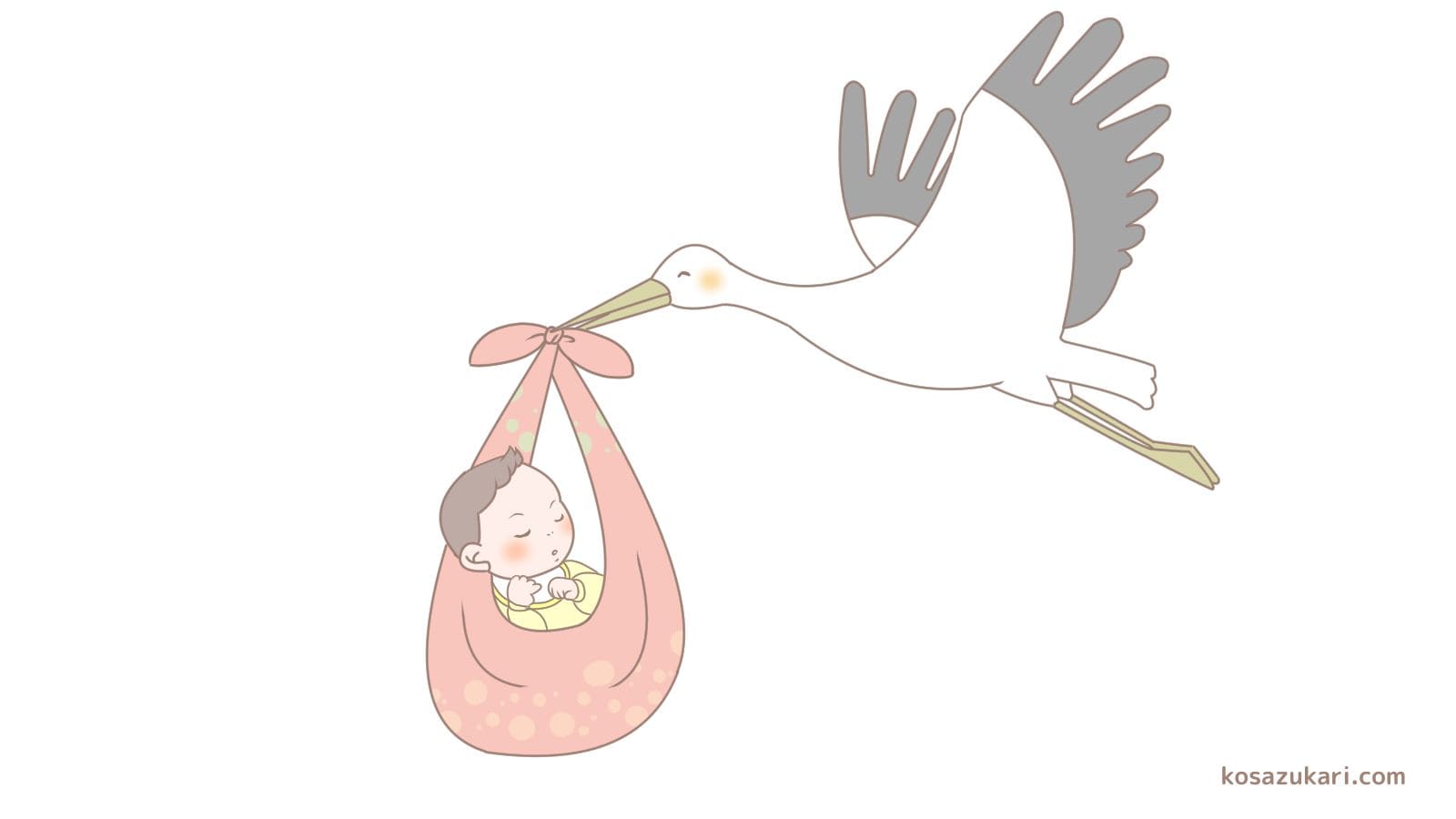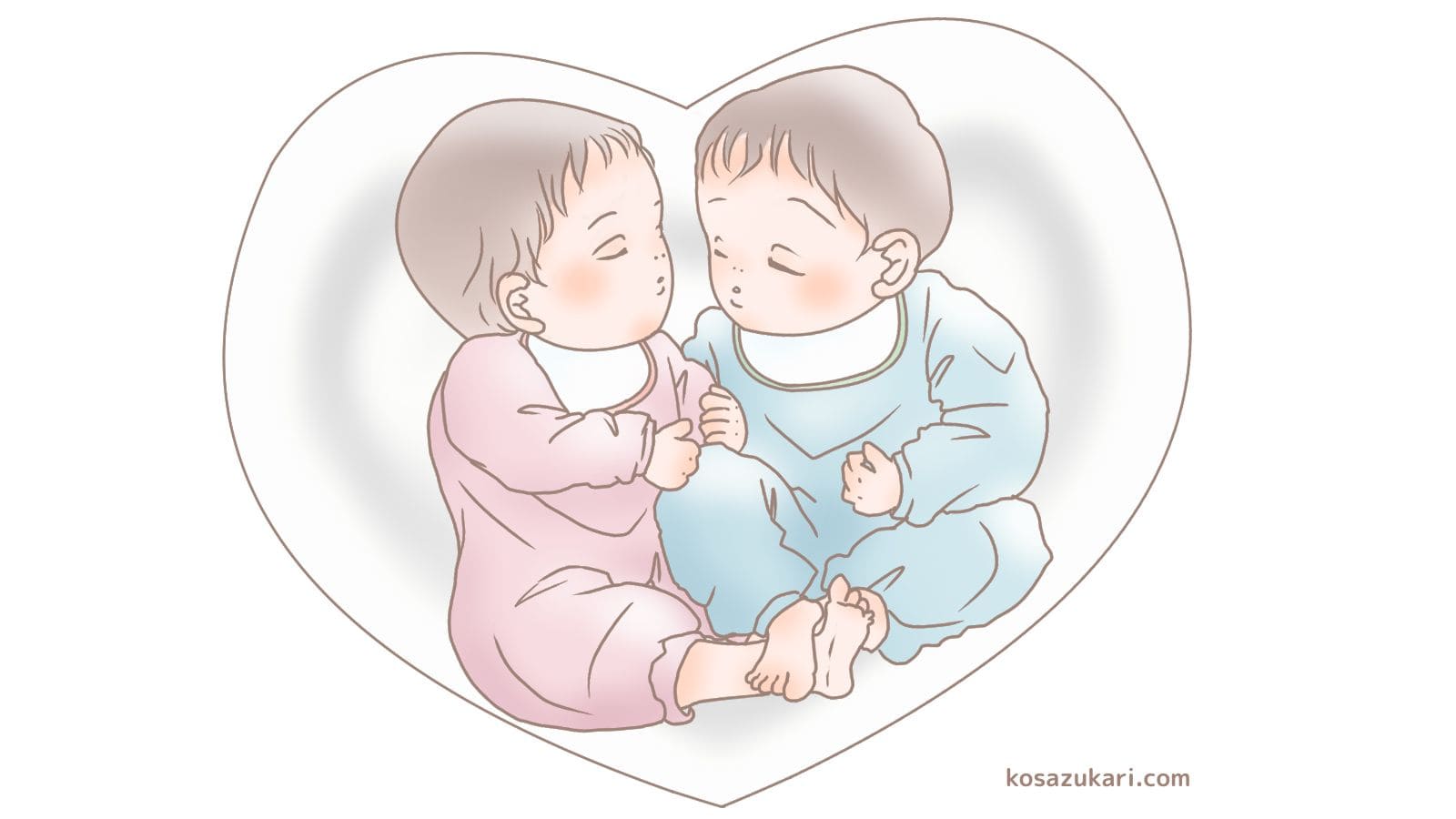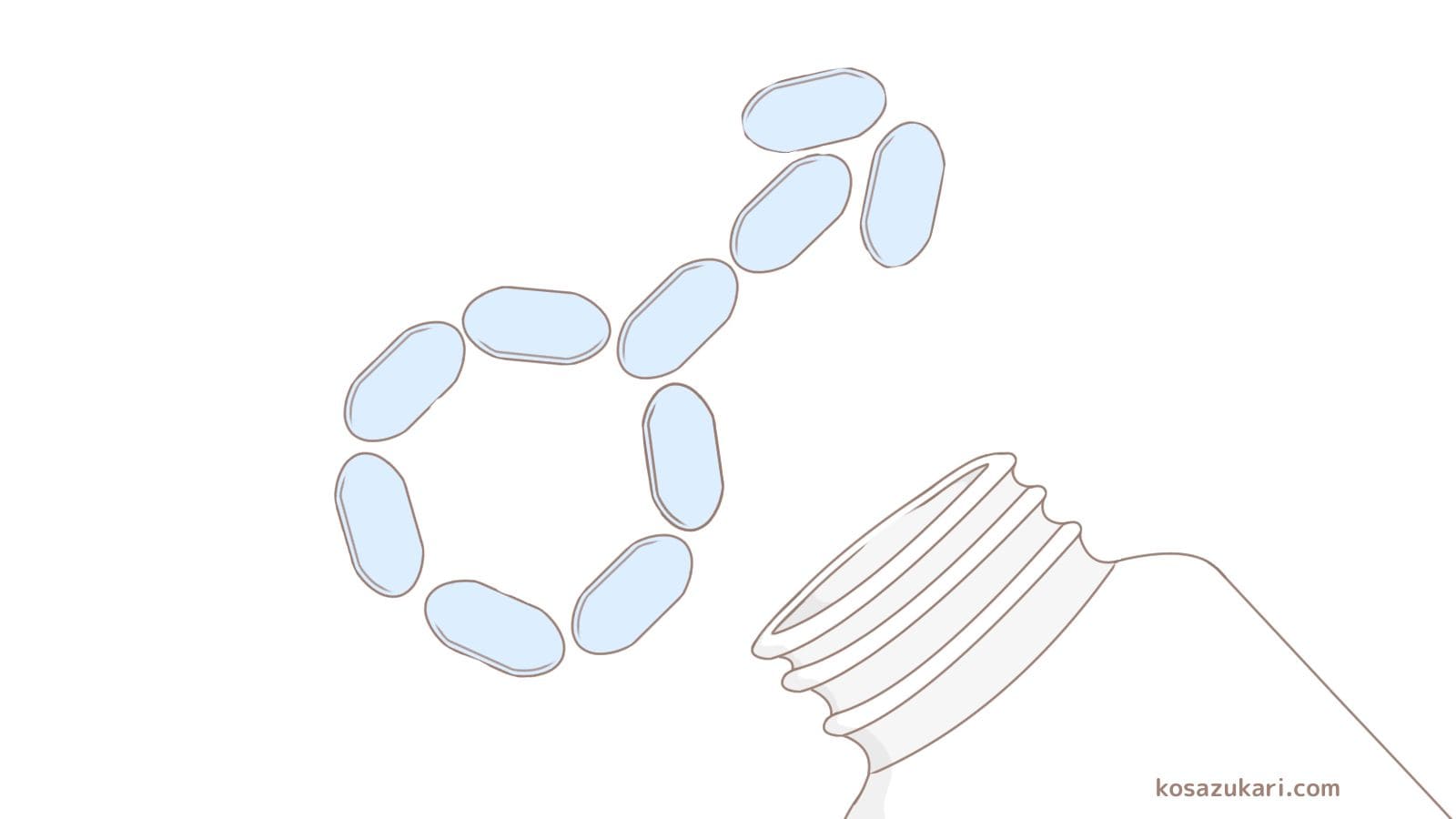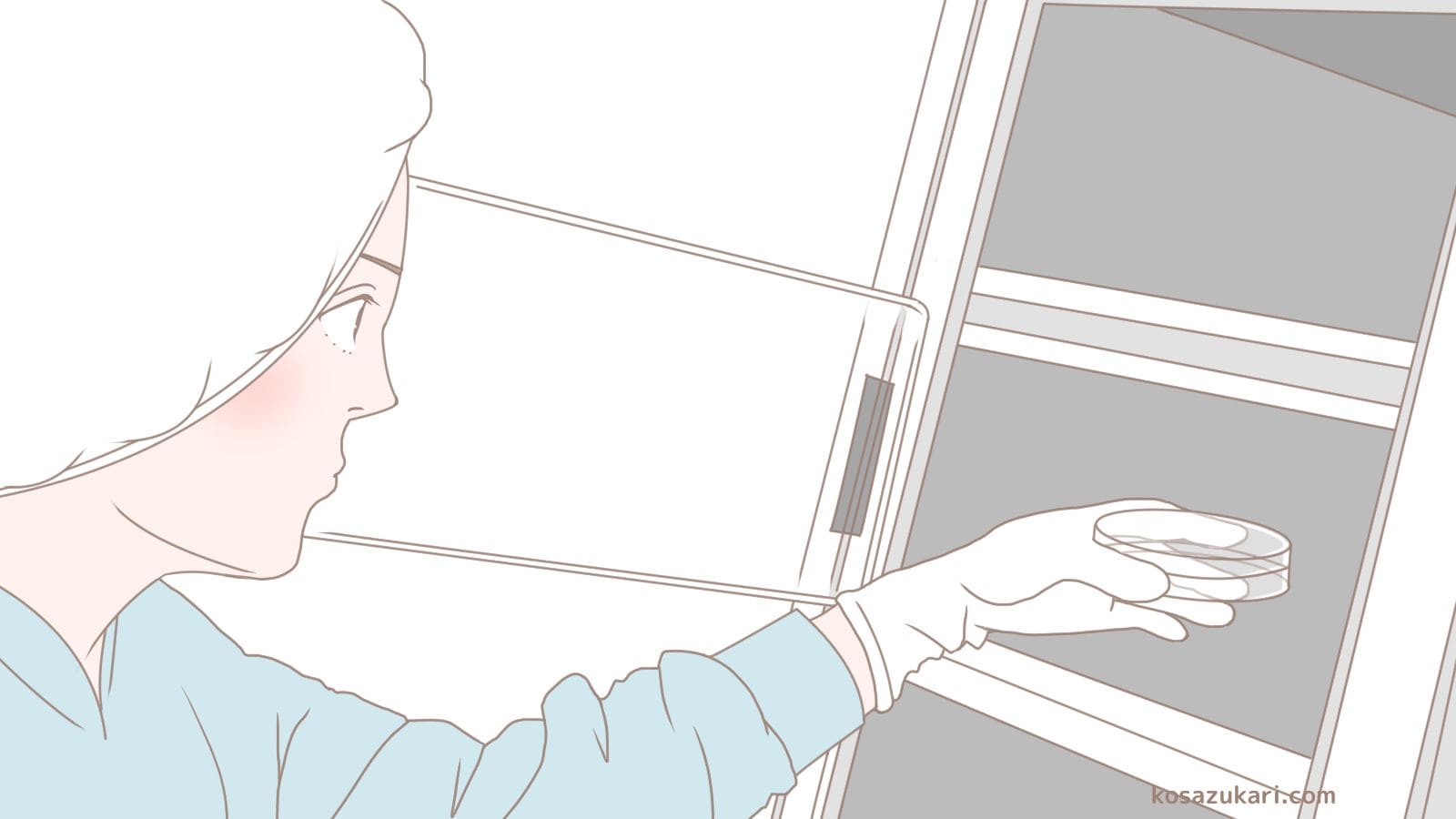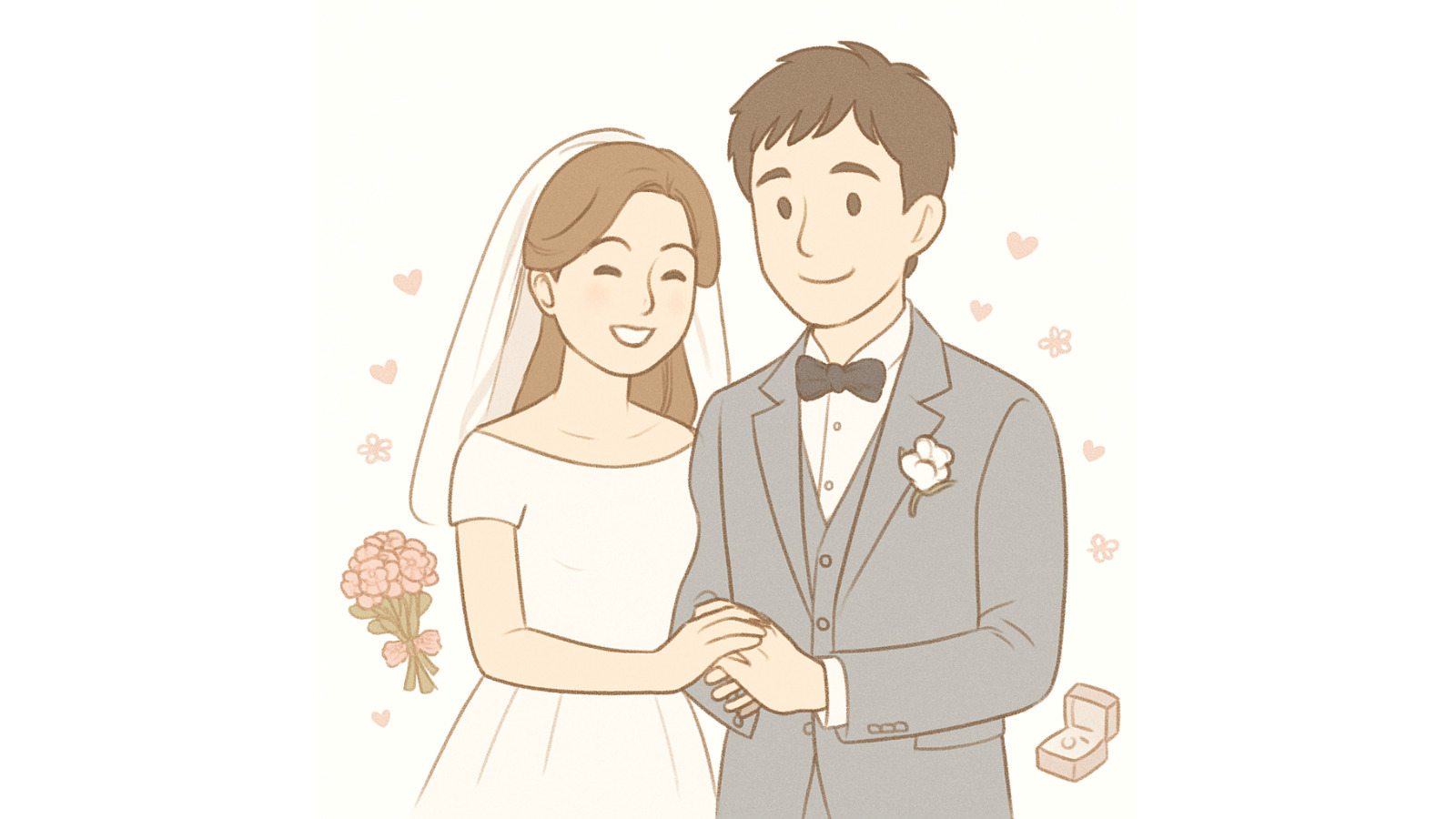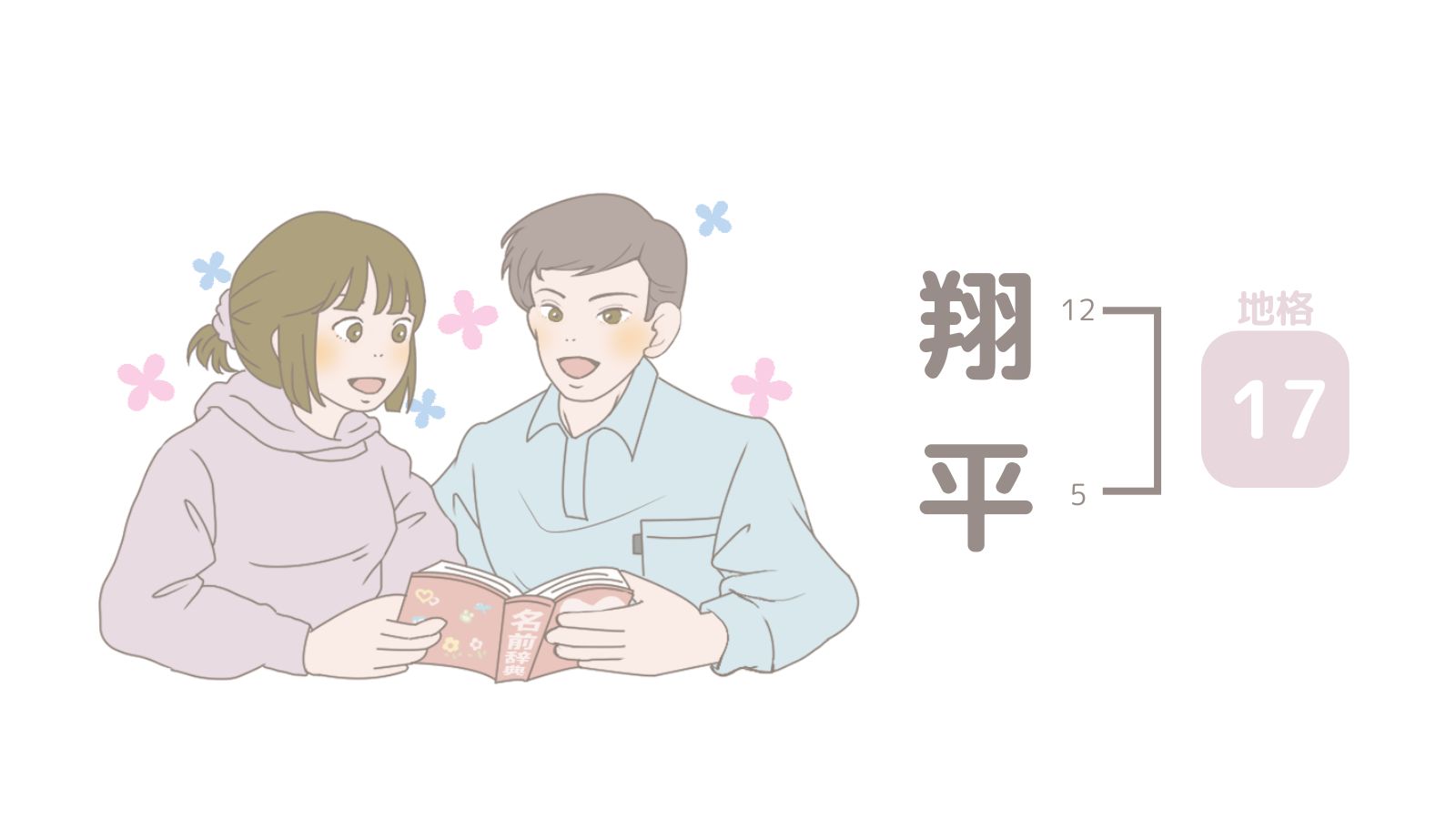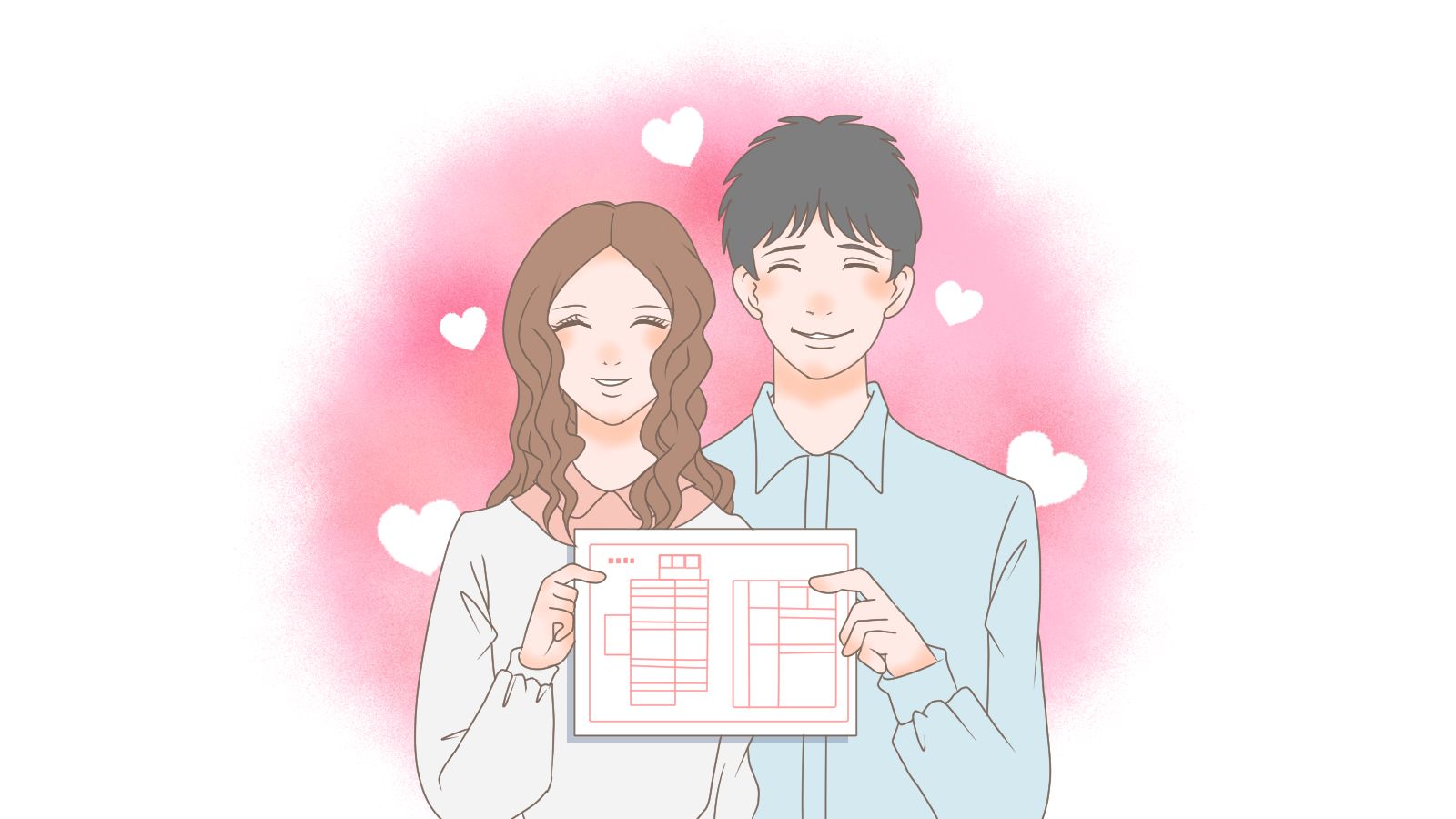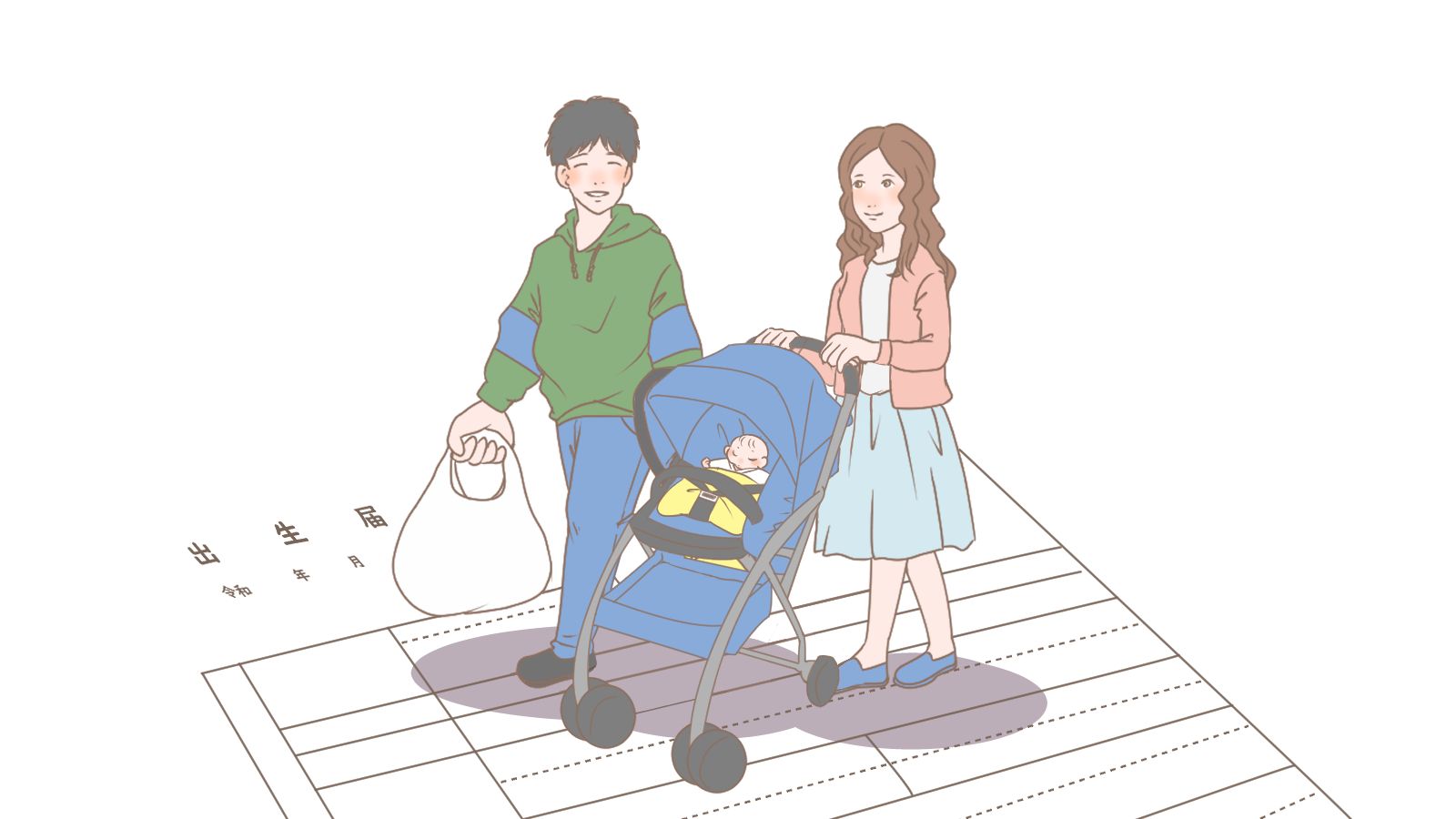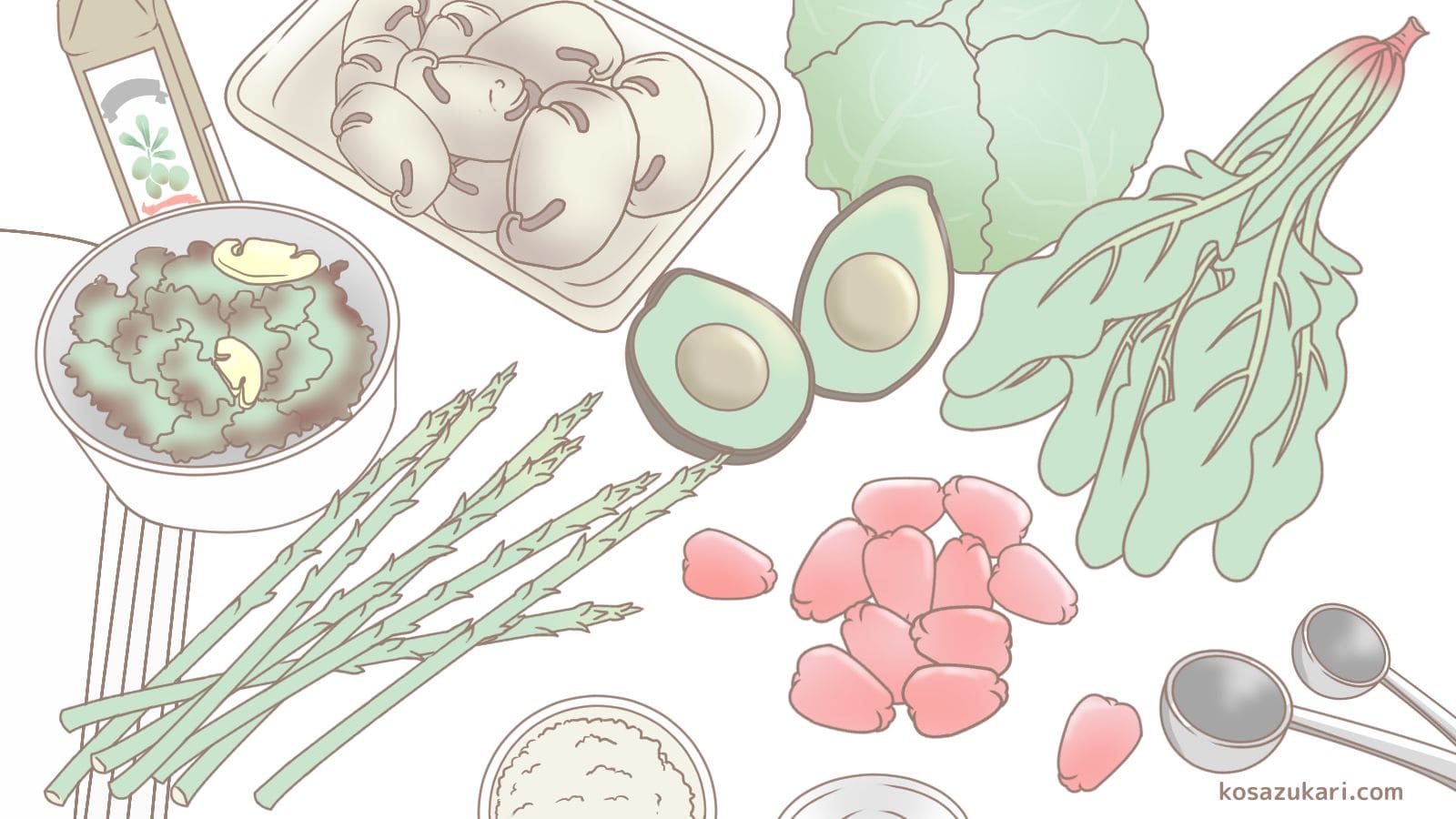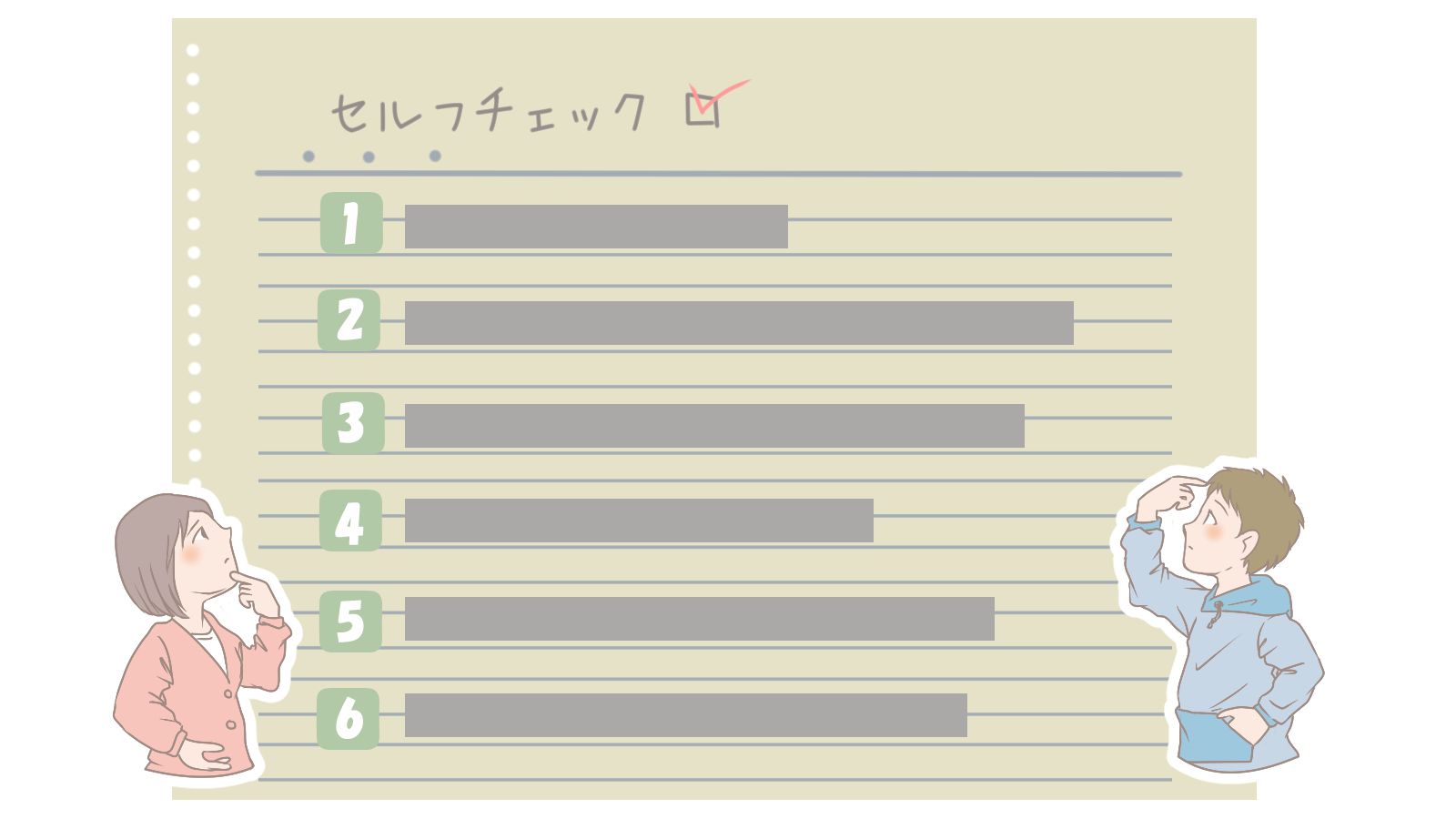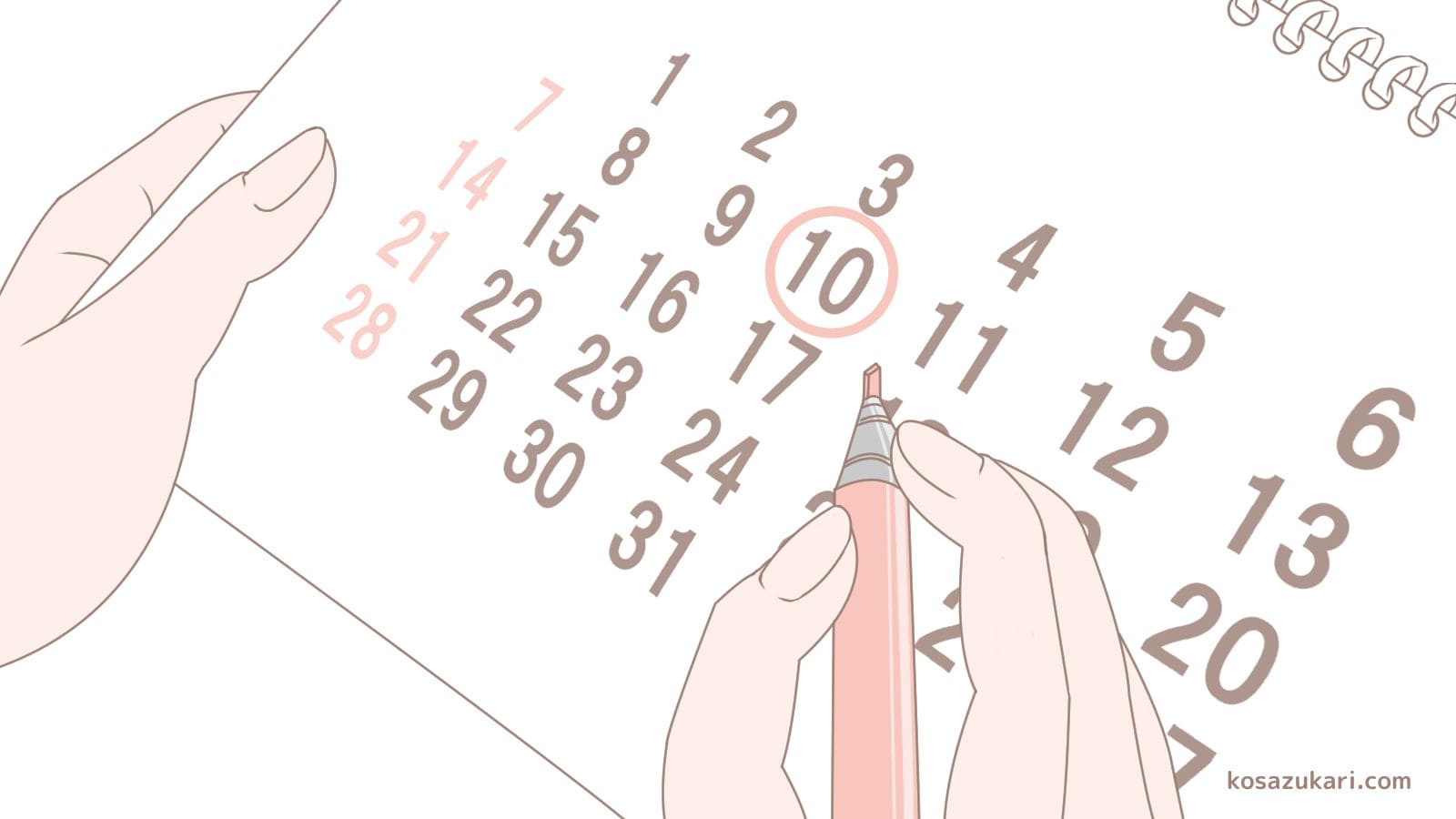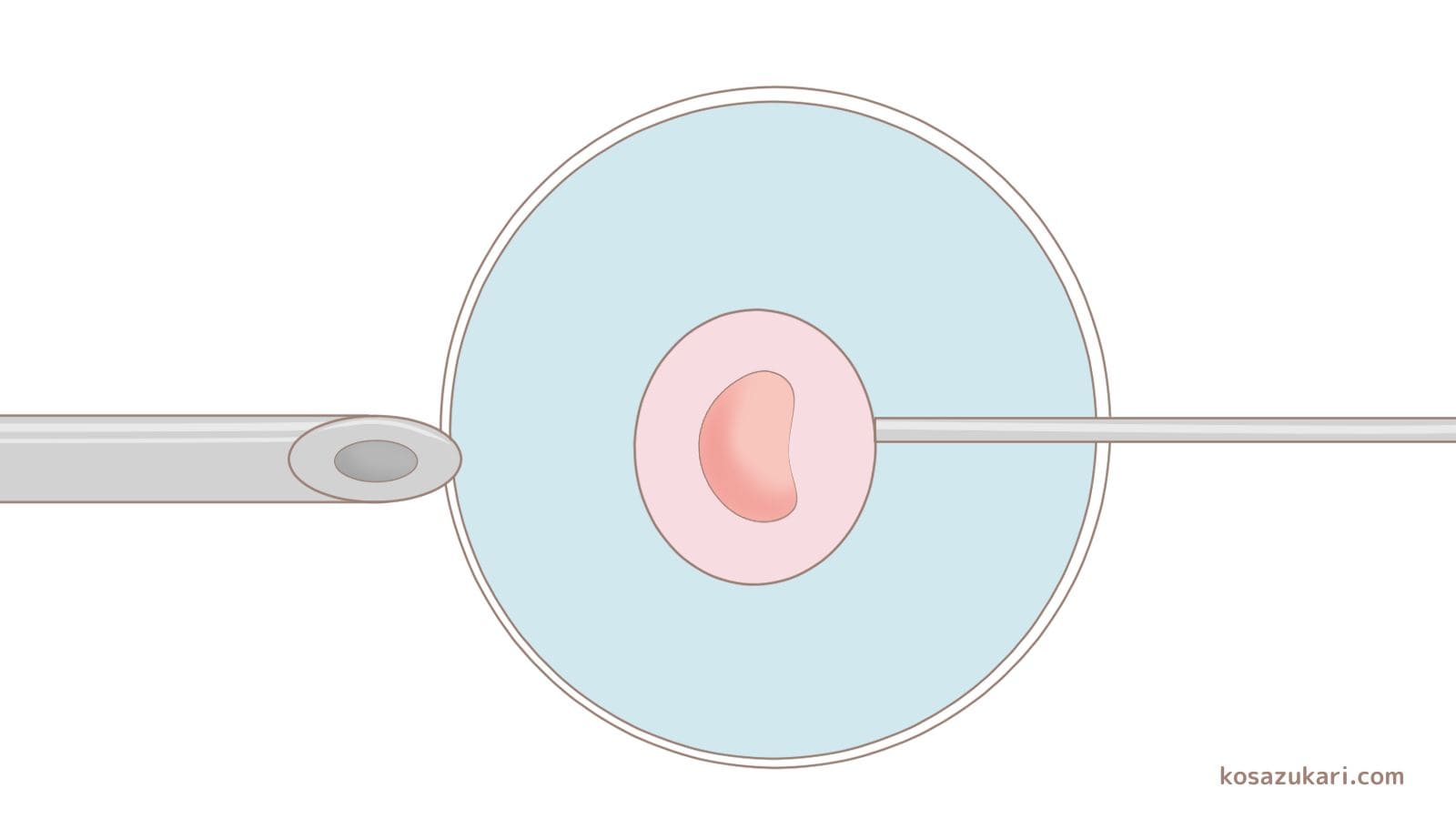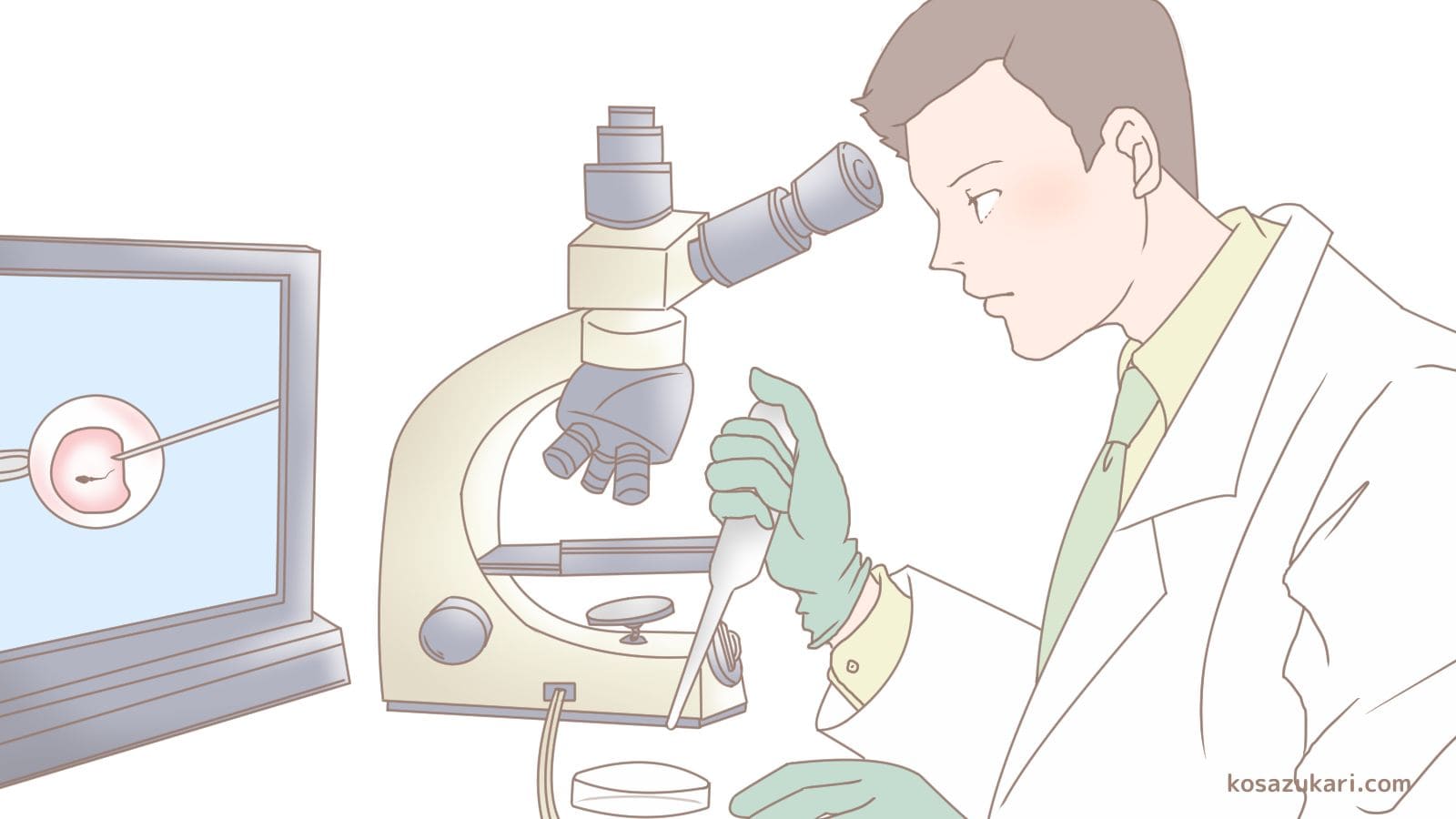子どもの斜視は、見た目の問題だけでなく「両眼で一つに見る力(両眼視)」や「奥行きを感じる力(立体視)」に影響します。ですが、早期発見と適切な治療で改善は十分に期待できます。本記事では、家庭で気づけるサイン(写真でのチェック法・仕草の変化)、タイプ別の原因と特徴、治療の選択肢(眼鏡・プリズム・視能訓練・手術)を専門医の視点でわかりやすく解説し、「いつ受診すべきか」「どこを受診するか」の目安まで具体的にお伝えします。今日からできる観察・記録・生活の整え方で、お子さまの視力と将来の見え方を一緒に守っていきましょう。
斜視とは?
斜視は「黒目の向きのズレ」によって、ものを両目で一つに見る力(両眼視)や奥行きを感じる力(立体視)に影響が出る状態です。まずは、どんなズレがあるのか、そして発達期の視機能にどんな影響が及ぶのかを、保護者の方にも直感的に理解できるよう整理します。
斜視の定義(内斜視/外斜視/上下斜視)
斜視(しゃし)とは、左右の眼が同じ目標に向かず黒目の向きがずれている状態をいいます。代表的には、黒目が鼻側へ寄る内斜視、耳側へ外れて見える外斜視、上下方向にずれる上下斜視があります。ずれが常に出る「恒常性」のタイプもあれば、疲れたときやぼんやりしたときに一時的に出る「間欠性」のタイプもあります。
見た目の問題にとどまらず、片方の目の像を脳が抑え込んでしまうことで両眼でものを一つにまとめる力(両眼視)や奥行きを感じる力(立体視)が妨げられることが重要です。
両眼視・立体視が育つ時期と「早期発見」の重要性
両眼視や立体視は乳幼児期から学童期にかけて発達する機能です。この時期に斜視が続くと、片眼の視力の伸びが不十分になる弱視や、立体視の発達不良につながるおそれがあります。
一方で、早期に気づいて適切な治療を始めれば改善が期待できます。気になるサインが続く場合は「様子見」に頼りすぎず、早めの受診が大切です。
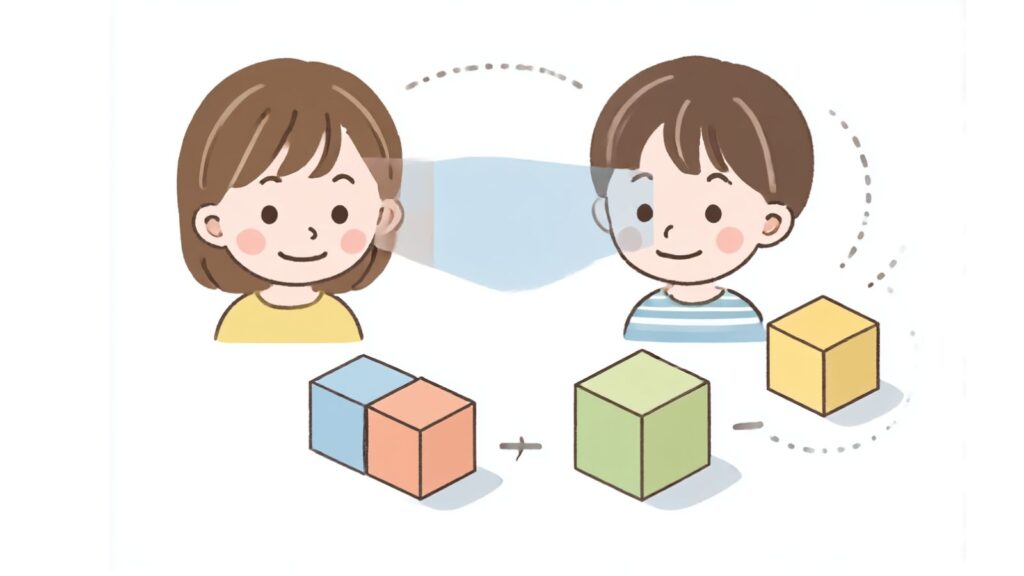
症状の見分け方:家庭で気づけるサイン
早めに気づくコツは、日常の中にある小さな変化を逃さないことです。見た目のズレや仕草、学校生活での困りごと、そして写真・動画でのチェックポイントを具体的に確認し、受診の判断につなげましょう。
見た目のサイン
- 正面から見たときに黒目の位置が左右で違う(片方が内側/外側/上下どちらかに寄る)
- 写真で光の反射位置が左右でずれる(フラッシュの白い点が左右非対称)
- 顔を傾ける・片目をつぶるなど、見え方を補う仕草が増える
行動サイン
- 学校で黒板が二重に見える/ぼやける、ノートの書き写しミスが増える
- 頭痛・眼精疲労・まばたきの増加、画面や本を極端に近づける
- 球技や階段で距離感がつかみにくい様子がある
写真チェックのコツ
- 正面・両眼開眼・まっすぐ見る状態で、スマホのフラッシュを用いて顔全体を撮ります。
- 瞳に映る白い反射点(角膜反射)が左右で同じ位置なら目線は概ね合っています。ずれていれば要注意です。
- 1回で判断せず、日を変えて数枚撮り、同じ傾向が続くか確認しましょう。家庭で記録した写真・動画は、受診時の有用な資料になります。

原因とタイプ別の特徴
斜視はタイプや背景によって対処法が異なります。年齢、屈折異常(遠視・左右差)、家族歴、生活環境などを手がかりに、代表的なタイプの違いと注意点をわかりやすく解説します。
調節性内斜視/先天性内斜視/間欠性外斜視の違い
- 調節性内斜視:遠視が背景にあり、近くを見るときの過剰なピント合わせ(調節)に伴って内寄り(輻輳)が強くなるタイプ。遠視矯正の眼鏡で改善が見込めることが多いです。
- 先天(乳児)内斜視:生後早期に発症し、ずれが大きいのが特徴です。早期の手術介入を含め、視力・両眼視の発達を守る計画が必要になります。
- 間欠性外斜視:疲労やぼんやりしたときに片目が外へ外れやすいタイプ。程度や頻度、両眼視機能の状態により、経過観察〜訓練〜手術まで幅広く選択します。
遠視・不同視・家族歴・発達背景とリスク
- 遠視・不同視(左右の度数差)があると、斜視や弱視のリスクが上がります。
- 家族歴がある場合も、早めのチェックが安心です。
- 発達・全身の背景、視力の伸び、生活習慣(近距離作業の多さ・屋外時間の少なさ)も総合的に評価します。

斜視は治る?治療の選択肢と期待できる経過
治療は「屈折矯正・プリズム・視能訓練」などの保存的アプローチから、必要に応じて「注射・手術」まで段階的に進めます。お子さまの年齢やズレの大きさ、両眼視の状態に合わせて、実現可能なゴールを一緒に考えていきましょう。
眼鏡(遠視矯正・プリズム)、視能訓練(ORT)
- 遠視矯正の眼鏡:調節性内斜視では第一選択。適切な度数で眼位が整いやすくなります。
- プリズム眼鏡:像をわずかにずらし、二重に見えるつらさを軽減します。
- 視能訓練(ORT):視能訓練士の指導で、両眼視の協調・立体視の回復をめざします。家庭でできる簡便な訓練が処方されることもあります。
ボツリヌス注射・斜視手術の適応とタイミング
- ボツリヌス毒素注射:一部の年長例で内側に引く筋の過緊張を一時的に弱め、眼位を整える目的で用いられることがあります。
- 斜視手術:ずれの角度が大きい、眼鏡や訓練で十分整わない、日常生活に支障が大きい場合などに検討します。目的は眼位の改善と両眼視機能の温存・回復です。手術後も視能訓練や眼鏡の調整を続け、再発予防と機能の安定を図ります。
弱視治療(遮閉など)と並行の考え方
斜視に弱視(片眼の視力発達が不十分)が並存する場合、遮閉(アイパッチ)やアトロピン点眼などで弱視眼の視力発達を促すことが重要です。「視力の基礎づくり」+「眼位の調整」+「両眼視機能の再構築」を並行して行うイメージで、年齢・発達・生活への影響を考えながら計画します。
受診の目安と受診先の選び方
「様子を見る」だけで時間が過ぎてしまわないよう、受診のサインを明確にしておくことが大切です。継続期間や生活への影響、写真・動画で確認できる所見を目安に、適切な医療機関(小児眼科・斜視専門)へスムーズにつなげる方法をお伝えします。
「いつ受診する?」チェックリスト
次のいずれかに当てはまる場合は、早めの受診をおすすめします。
- 黒目のずれ・片目閉じ・顔の傾きなどが2週間以上目立つ
- 二重に見える/頭痛/読みづらさなど、学習や生活に支障が出る
- 正面フラッシュ写真・動画で繰り返し同じズレが確認できる
- 乳幼児で生後早期からはっきりした内寄りがある
小児眼科・斜視専門外来の探し方/受診時に持参すると良いもの
- 受診先は、小児眼科や斜視専門外来のある医療機関が望ましいです。各学会の医療機関リストや地域の基幹病院を目安に探しましょう。
- 持参すると診断に役立つもの:
- ・正面フラッシュ写真(角膜反射の左右差がわかる)
- ・遠近切替の動画(片眼の動きの遅れ・停止がないか)
- ・学校の視力検査結果・担任の所見(板書の見えづらさ等)
- ・これまでの眼鏡・治療歴

まとめ:今日からできること
まずは家庭での観察と記録から。距離・時間・姿勢・明るさを整え、気になる変化が続くときは早めに専門医へ相談しましょう。
家庭での観察ルーティンと生活上の工夫
- 月1回の定点フラッシュ写真+気になる時期のスポット撮影で記録を残す
- 距離(30cm以上)/連続時間(30分ごとに休憩)/姿勢(椅子+背もたれ)/明るさを整える
- 屋外活動を増やし、近距離作業に偏らない1日を意識する
(引用元)
日本眼科学会:子どもの斜視
公益社団法人 日本眼科医会:子どもの斜視
国立成育医療研究センター:若年者の後天共同性内斜視(AACE)に関する報告
MSDマニュアル家庭版:斜視
本記事は上記の公的・専門情報をもとに、保護者が実践しやすい形に再構成しています。診断・治療方針は必ず担当医の指示に従ってください。